生成AIを活用したデータ分析は、ビッグデータを瞬時に解析し、売上の傾向や顧客ニーズの変化の把握に役立ちます。一方で、「生成AIで本当に正しいデータ分析ができるの?」「AIの回答を経営判断に使用して問題ない?」という不安の声も少なくありません。
そこで今回は、生成AIを使ったデータ分析の仕組みやメリット・デメリット、おすすめ生成AIツール、導入事例、具体的なアクションを解説します。
生成AIでデータ分析できる?【ビッグデータを迅速に分析可能】
生成AIを分析ツールとして活用することで、データの収集や解析プロセスを効率化できます。例えば、売上データや顧客情報を素早く処理し、今後の傾向をつかむことで、経営判断の精度を高められます。
また、Excelの自動化機能と組み合わせることで、データ整理からグラフ作成までをスムーズに進められます。これにより、作業負担が軽減されるだけでなく、分析の精度も向上します。
市場調査や競合のチェックといった場面でも、生成AIは関連する情報を幅広く拾い上げて整理できるため、これまで見落としていたポイントにも目が届くようになります。
こうして得られた情報は、消費者のニーズや流行の変化をとらえたマーケティング施策へとつなげることができます。結果として、素早く行動に移せるようになり、生成AIは頼れる分析ツールとして、日々の意思決定を後押しする存在となるでしょう。
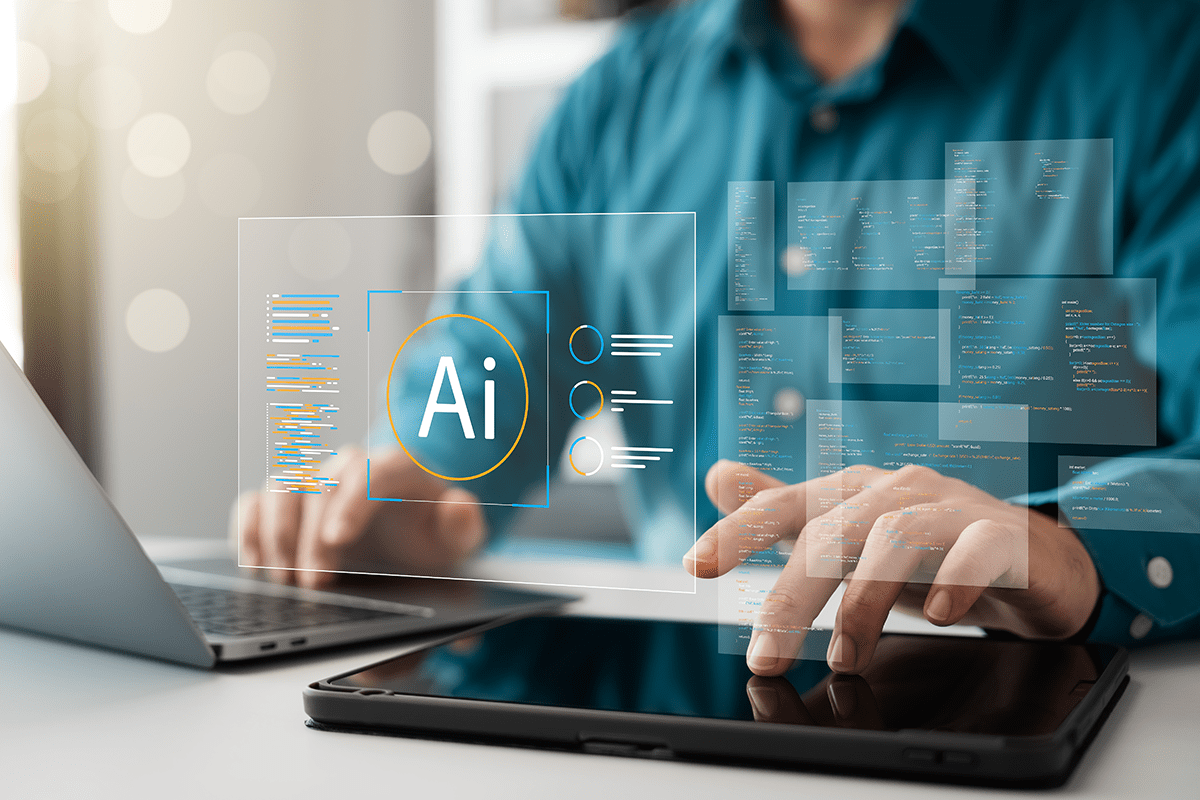
データ分析を生成AIで行うメリット
生成AIを活用してデータ分析を行うメリットは以下の通りです。
ここからは、データ分析を生成AIで行うメリットをそれぞれ解説します。
状況を正しく理解できる
生成AIはビッグデータ(膨大なデータ)の中から相関関係を抽出し、通常の分析では得られない新たな切り口を発見できます。
例えば、小売業では購買履歴を分析することで、ヒット商品の企画や販売戦略の策定が可能になります。医療分野でも、患者データの傾向を分析することで、治療方針の補強につながる新たな発見が得られるケースがあります。
さらに生成AIは、分析結果を基に新たな仮説やアイデアを提案する能力を持っています。現状の把握にとどまらず、将来に向けた行動や新たな提案へと発展させやすい点も、大きなメリットと言えます。
迅速かつ効果的な意思決定ができる
生成AIは、人間では時間がかかるビッグデータ(膨大なデータ)の処理を素早く行い、判断に必要な情報を短時間でまとめることができます。その結果、これまでよりも速く次のアクションに移れるようになります。
また、生成AIの出す結論は感覚や思い込みに左右されにくく、客観性が高いのも特徴です。論理に基づいた選択肢が得やすくなり、課題解決のスピードを速めることができます。
さらに、膨大で複雑な情報を整理したうえで、複数の対応案を自動で提示することも可能です。これにより、意思決定のプロセスそのものがシンプルになり、スピードと正確さを両立した判断がしやすくなります。
将来の予測ができる
生成AIを分析ツールとして導入することで、さまざまなビジネステーマを高精度に予測できます。そのため、幅広い分野で生成AIの活用が進んでいます。
深層学習をベースにした時系列解析によって、従来の重回帰分析では複雑だったパターンや、長期的な傾向も把握しやすくなります。これにより、業務の効率化だけでなく、意思決定の質も向上するでしょう。
さらに、生成AIは予測結果をもとに、新たな仮説やアイデアを提案することも可能です。マーケティング施策や製品開発において、より創造的かつデータに基づいたアプローチを実現しやすくなります。生成AIの柔軟性と応用力の高さは、企業活動において大きな価値をもたらします。
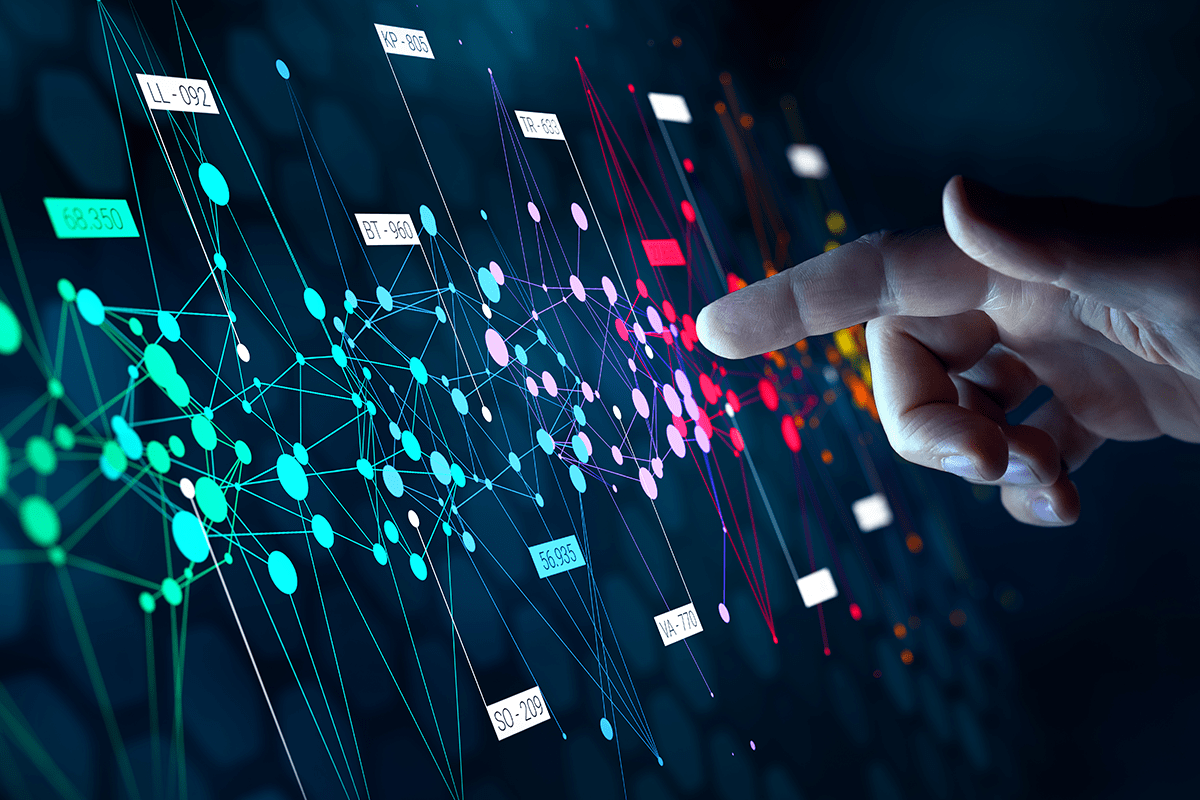
生成AIをデータ分析に使うデメリット・注意点
生成AIをデータ分析に活用することで得られるメリットは多いですが、以下のように、注意すべき点も存在します。
ここからは、生成AIをデータ分析に使うデメリット・注意点をそれぞれ解説します。
出力結果の精度にばらつきが生じる
生成AIは膨大なデータを解析できますが、複雑な変動がある場合に結果の精度が低下するケースがあります。そのため、検証のプロセスを必ず挟み、人間の専門知識で補うことが重要です。
特に、経営判断や提出用のレポートといった重要な場面では、出力された数値に統計的な誤差が含まれていないかを確認する必要があります。また、AIの活用範囲をあらかじめ明確にしておくことで、どこまでを自動化してどこまでを人間が判断するのかを整理でき、リスクを抑えた運用が可能になります。
数値処理に弱みがある
GPTやGeminiといった大規模言語モデルの生成AIは、言語パターンの予測をベースに動作しているため、数値計算の精度には限界があります。例えば、4桁同士の掛け算のような複雑な演算などでは、誤った数値を出力することがあります。
生成AIが返す数値は、予測に基づいた仮の結果であり、数学的な正確性が完全に保証されるものではありません。特に重要なビジネス判断に使う場合には、ファクトチェックや再計算を行い、結果の信頼性を保つことが重要です。
誤った情報(ハルシネーション)を出力するリスクがある
生成AIを使ったデータ分析では、入力データに不備や偏りがあると、AIが誤った解釈をしてしまい、現実とはかけ離れた結論を算出する可能性があります。また、元データが正確であっても、推論の過程で誤って認識するケースも完全には避けられません。そのため、AIが出力する結果は、実際のデータや事実と照らし合わせ、妥当性を確認しましょう。
特に生成AIには、事実と異なる内容を作り出してしまう「ハルシネーション」のリスクがある点にも注意が必要です。このリスクを前提としたうえで、あらかじめ活用の範囲や目的を明確にし、「生成AIからの回答はあくまで参考」として扱う姿勢が求められます。こうしたリスク管理と検証の体制を徹底できれば、生成AIはデータ分析における信頼性の高い補助ツールとして、安全かつ効果的に活用できるでしょう。
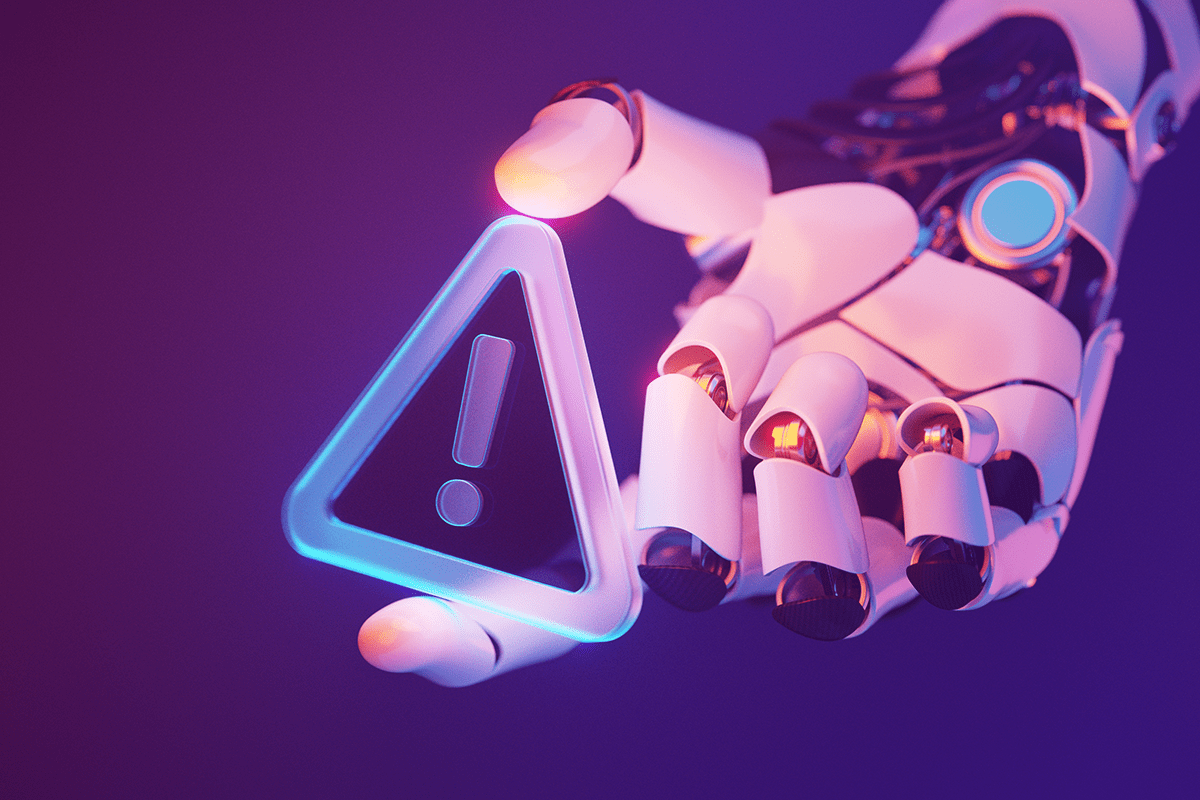
データ分析におすすめの生成AIツール
データ分析を行える生成AIは、さまざまな種類があります。そのため、目的に合った生成AIツールを選ぶことが重要です。以下では、データ分析におすすめの生成AIツールを紹介します。
Advanced Data Analysis:ファイルから自動分析・グラフ化
ChatGPTの「Advanced Data Analysis(旧Code Interpreter)」は、ExcelやCSV、画像ファイルなどをブラウザ上でアップロードするだけで、データのクリーニングから可視化までを行える生成AI機能です。ユーザーは、テキストで質問や指示を入力するだけで操作できます。
入力された内容に応じて、システムがPythonなどのコードを自動的に生成・実行する仕組みになっています。そのため、プログラミングの知識がなくても、高度な統計解析や予測モデルの構築が可能です。
さらに、音声や画像データの処理といった複雑なタスクも、手軽に実行できます。また、出力された結果をもとに、レポートやプレゼン資料の作成まで支援してくれる点も特徴です。データの読み込みから意思決定までの流れを効率化でき、大幅な作業時間の短縮が期待できます。
Copilot in Excel:Excel内でデータ分析
Copilot in Excel は、Excel上でグラフやピボットテーブルを対話的に生成しながら、データを視覚的に分析できるツールです。さらに、複雑な関数や計算式もAIが自動で提案・修正してくれるため、関数の知識があまりないユーザーでも、比較的高度な解析を行うことができます。
また、VBAのようなコード処理にも対応しており、マクロの作成や業務自動化など、分析から実行までの流れを効率よくサポートします。
Tableau GPT:チャット形式で自動グラフ作成
Tableau GPT は、自然言語による質問とビジュアル分析を組み合わせて使える、生成AI搭載のBIツールです。専門的な知識がなくても、直感的にデータを読み解ける点が特徴です。ダッシュボード上から必要な指標にすぐアクセスできるため、レポート作成や分析にかかる時間を短縮できます。
さらに、予測モデリングやビジネスサイエンス、拡張分析などの高度な機能も備えており、複雑なシナリオ分析や将来予測を、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で行えます。
Chartify:無料でグラフやチャートを作成
Chartify は、専門的な知識がなくても、直感的な操作だけでデータを美しいグラフに変換できる生成AIツールです。フォントや配色、レイアウトの調整も柔軟に行えるため、ビジネスレポートや教育資料、プレゼンなど、目的に応じた見やすいビジュアルを手軽に作成できます。
視覚的に整理されたチャートは、データの意味を素早く伝えることができ、気づきの共有や分析の効率化にも役立ちます。
QuickSight Generative BI:チャット形式でダッシュボードを作成
AWSのQuickSight Generative BI は、機械学習アルゴリズムを活用し、データのパターンや外れ値を自動で検出できるBIツールです。人間では見落としがちな傾向や例外も、瞬時に可視化できます。
また、自然言語で指示を出すだけで、インタラクティブなダッシュボードを構築できる点も特徴のひとつです。チーム全体で分析結果を素早く確認できるため、情報の行き違いを防ぎつつ、意思決定のスピードと正確さを同時に高められます。
QuickSightでは、毎週数百万回にのぼるダッシュボードビューが確認されており、大規模な組織にも十分対応できる信頼性を持っています。作成したレポートや分析結果は、ワンクリックで簡単にチーム内や社外に共有することができます。
Rows:スプレッドシートを自動分析
Rows は、コードを書くことなく、SNSや広告プラットフォームなどの外部サービスからデータを簡単に取り込める分析ツールです。取得したデータはすぐに分析に活用できます。
また、GPT-3が組み込まれており、自然言語でのQ&Aやデータ生成、フィードバックの自動分類といったタスクにも対応可能です。表の作成や整形も生成AIがその場でサポートしてくれるため、日常の作業がよりスムーズに進められます。さらに、作成したシートはオンラインで共有できます。
データ分析に生成AIを導入した事例
生成AIをデータ分析に導入した企業は、業務効率と顧客満足の両面で成果を上げています。以下ではコンビニとECプラットフォームの事例を紹介します。
生成AIで発注業務の自動化と需要予測を実現
セブン-イレブン・ジャパンは、2023年に全国の店舗へ生成AIを活用した発注分析ツールを全面導入しました。この導入によって、在庫が減ってから手入力で注文していた従来の発注方法から、AIによる提案型の運用へと切り替えています。
新システムでは、天候や曜日、過去の販売実績などのデータをリアルタイムで解析し、欠品が起こる前に最適な補充数をリアルタイムで自動提案します。その結果、品切れリスクの抑制に加えて、発注業務にかかる時間を約40%削減することに成功しました。
削減された業務負担は、スタッフが品揃えの強化や売場づくりに集中できるようになり、少人数でも効率的な店舗運営が可能となりました。これにより、顧客にとっても買いやすい環境づくりが進んでいます。
生成AIで出品商品の改善提案を自動化
メルカリは、生成AIと大規模言語モデルを活用した「メルカリAIアシスト」をアプリに初めて搭載し、ユーザーごとに最適な行動を提案するアシスタント機能の提供を開始しました。その第一弾として導入されたのが、「出品商品の改善提案機能」です。
これは、一定期間売れ残っている商品に対して、過去の販売データをもとに分析を行い、より売れやすくなるよう改善点を提案するものです。例えば、商品名の自動生成や、サイズ・価格情報の追記といった具体的なアドバイスが提示されます。
現時点では一部のカテゴリに限定して段階的に展開されていますが、出品者の作業負担を軽減しながら、販売チャンスの最大化を目指す取り組みとして注目されています。また、売れにくかった商品に再び関心を集めるきっかけとなることも期待されています。
生成AIでデータ分析をする際の具体的なアクション
生成AIをデータ分析に活用するには、まずその仕組みや活用範囲を理解し、自社の業務や課題と結び付けて可能性を見極めることが出発点となります。次に、信頼できる結果を得るためには、データの品質を管理し、生成AIを動かすためのインフラを整備しておく必要があります。この段階で、導入の基盤が整います。
そのうえで、生成AIの専門家やベンダーと連携し、外部の知識を取り入れながら、最適な運用体制を築いていくことが大切です。導入後は、モデルの精度やビジネスへの効果を定期的に確認しながら、データの更新やパラメータの調整、運用フローの見直しを継続的に行いましょう。こうしたプロセスを繰り返すことで、生成AIのパフォーマンスを継続的に高めていくことができます。
まとめ
今回は、生成AIを使ったデータ分析の概要やメリット・デメリット、おすすめのツール、成功事例、導入までのアクションを解説しました。
生成AIは、データ分析のスピードと精度を飛躍的に高め、業務効率や意思決定の質を向上させる有効な手段のひとつです。一方で、精度のばらつきやハルシネーションといったリスクもあるため、人による検証やガバナンス体制の整備は欠かせません。
ぜひ、自社の目的に合わせて生成AIをデータ分析に取り入れ、競争力の強化につなげてみてください。


