生成AIを自社で活用するには、オープンソースのものを使用する必要がありますが、「オープンソースの生成AIの特徴やメリットは?」「オープンソースの生成AIの導入方法は?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、オープンソースの生成AIの概要や活用のメリット、代表ツール、導入方法を解説します。
オープンソースの生成AIとは?【制限なく使用できるAI】
オープンソースの生成AIとは、AIモデルやソースコードが一般向けに公開されており、誰でも制限なく使用できるAIシステムを指します。オープンソースの生成AIには、主に以下の自由が認められています。
オープンソースの生成AIは、目的に応じたカスタマイズや機能追加が可能ですが、本格的な運用にはAIに関する専門知識とスキルが必要です。
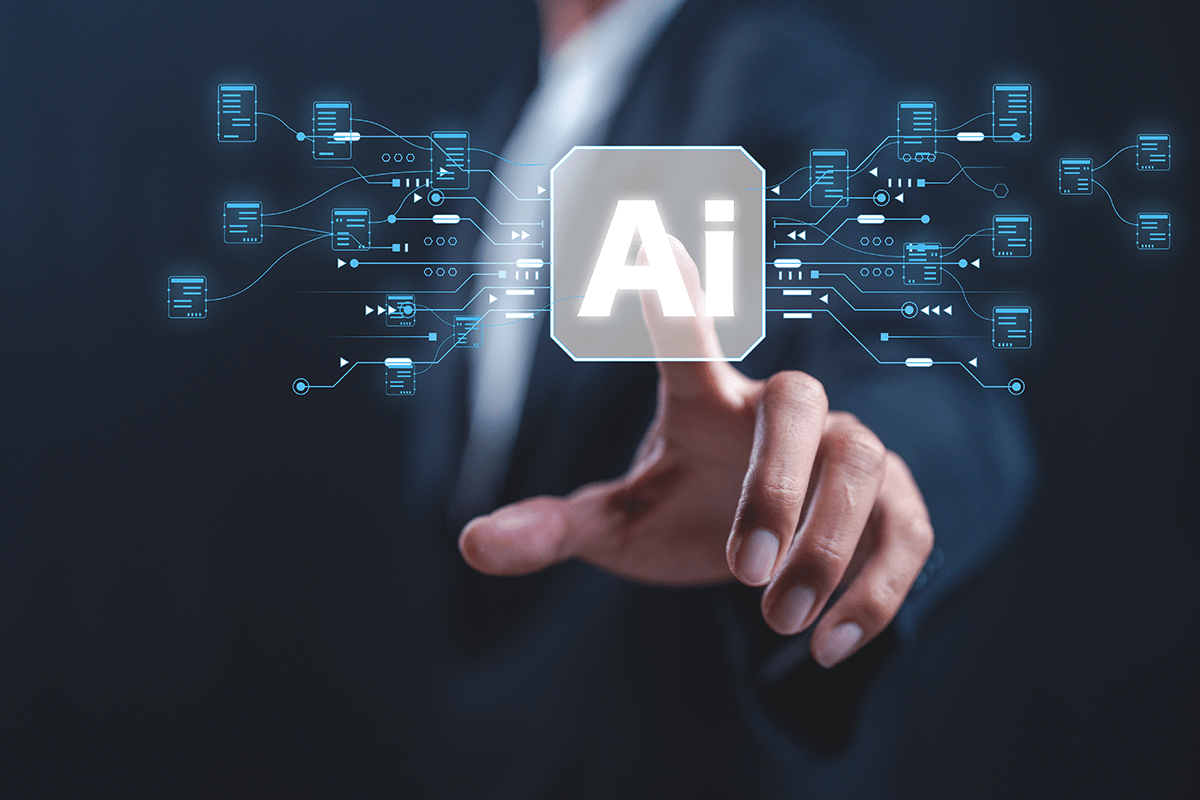
オープンソースの生成AIを使うメリット
オープンソースの生成AIは、主に以下のメリットがあります。
ここからは、オープンソースの生成AIを使うメリットをそれぞれ詳しく解説します。
柔軟な構成と高精度運用が可能
オープンソースの生成AIは、サーバーや周辺機器を含めたハードウェアやソフトウェアを自社の業務体制に合わせて組み合わせることができます。自社に合わせたカスタマイズを行うことで、操作性や処理効率を高めることが可能です。
例えば、AIモデルのファインチューニング(学習済みのデータを使用目的に合わせて調整する手法)やRAG(検索拡張生成)のような機能追加も自由に行えます。自社の専門業務に応じて、生成精度を高め、より実用的な出力が得られるように調整することもできます。
さらに、インフラ構成を全て自社で管理できます。特定の事業者に依存せずに済むため、リスクを分散しながら、より柔軟で効率的な運用ができます。
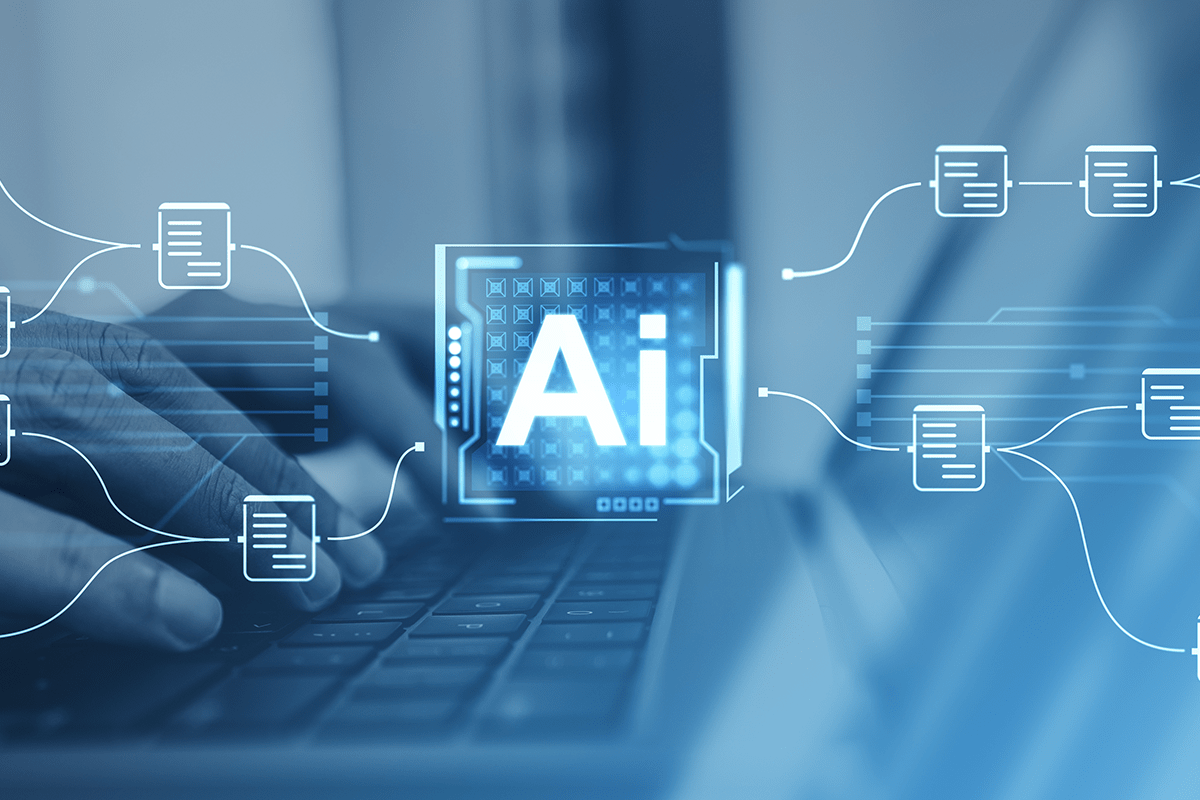
長期的なコスト削減と支出の見通しが可能
オープンソースの生成AIは、大規模言語モデル(LLM)を含めて利用料金が発生しません。そのため、商用の生成AIと比較すると、開発コストを大幅に抑えることができます。一方で、自社内でサーバーやネットワーク環境を整備する初期投資は必要です。
特にサブスクリプション料金と比べると、オンプレミスでの運用は保守費用のみで済むケースが多く、使用量に応じた追加コストも発生しません。長期的には全体の支出を抑えやすく、予算の見通しも立てやすくなります。その結果、より安定した運用計画を立てられる点も大きなメリットです。
セキュリティと信頼性の強化
オープンソースの生成AIを社内ネットワークだけで運用すれば、処理データが社外へ流出せず、情報漏えいや不正アクセスのリスクを最小限に抑えられます。
また、インターネットを介さない生成AIはサイバー攻撃の標的になりにくく、セキュリティ監査の際に安全性を証明しやすいです。
さらに、モデルの推論ロジックや学習プロセスを詳細に把握できるため、出力の根拠を説明しやすく、業務の信頼性向上に役立ちます。
主なオープンソースの生成AIツール
オープンソースの生成AIには、用途に応じてさまざまな種類のツールが存在します。ここでは、テキスト生成・画像生成・コード作成・フレームワークという4つの分野から、代表的なオープンソースAIを紹介します。
下記の表では、各ツールの主な特徴と日本語対応の有無をまとめています。
分野 | ツール名 | 主な特徴 | 日本語対応 |
テキスト生成 | Llama | 15兆トークンで学習、高精度・商用利用可。 | 〇 多言語版あり(日本語学習済みモデルも公開) |
テキスト生成 | GPT-NeoX | 分散学習対応、Apache 2.0ライセンス。 | △ 日本語特化派生モデル「GPT-NeoX-Japanese」で利用可 |
テキスト生成 | OpenChat-3.5 | GPT-3.5に相当する性能。 | 〇 多言語入力に対応(日本語可) |
画像生成 | Stable Diffusion | 潜在拡散モデル。安全性・カスタマイズ性が高く、商用・非商用で利用可能。 | 〇 日本語プロンプト対応 |
画像生成 | Kandinsky 2 | DALL-E 2と Latent Diffusionを融合したモデル。Hugging Face Space でデモ利用可。 | 〇 日本語プロンプト可(推奨は英語) |
コード生成 | Code Llama | 補完・デバッグ・説明生成に対応し、多言語をカバー。 | △ 一部対応(推奨は英語) |
コード生成 | StarCoder2 | 619言語対応、ファインチューニングが容易。 | 公式表記なし |
フレームワーク | Llama.cpp | C++実装。軽量。MITライセンス。 | 〇 モデルが日本語対応なら可 |
フレームワーク | LangChain | LLMと外部ツールを連携し、RAGやエージェントを構築できる。 | 〇 LLMが日本語対応なら可 |
テキスト生成AI
Meta社のLlamaシリーズは、対話や翻訳、コード生成など、幅広い自然言語処理に強みを持つ大規模言語モデルです。最新版のLlama3は、15兆トークンを用いて学習されており、精度が大きく向上しています。Llama2以降はソースコードが公開され、商用利用も可能です。英語が中心ではあるものの、Meta社による多言語対応により、日本語を学習した派生モデルも存在します。
EleutherAIのGPT-NeoXは、数十億パラメータ規模の大規模モデルを効率よく訓練するためのライブラリです。分散学習やbfloat16(Brain Floating Point Format)に対応している点が特徴で、Apache License 2.0のもと、無償で利用できます。日本語に特化した「GPT-NeoX-Japanese」も提供されています。
OpenChat-3.5は、独自のC-RLFT学習によって、品質と開発コストのバランスを両立した軽量モデルの生成AIです。70億(7B)パラメータでGPT-3.5 相当の性能を発揮します。ソースコードは無料で公開されており、日本語の入力・出力にも対応しています。
画像生成AI
Stable Diffusionは、潜在拡散モデル(Latent Diffusion Model)を採用し、与えられたテキストから高品質な画像を生成できるオープンソースの画像生成AIです。安全性やカスタマイズ性にも優れており、商用・非商用を問わず利用できます。ライセンス条項を遵守すれば、生成された画像の著作権はユーザーに帰属します。日本語のプロンプトにも対応していますが、英語プロンプトに比べてやや精度が劣ります。
Kandinsky 2は、Sber AI Labによって開発されたロシア発の画像生成モデルです。DALL·E 2のテキスト処理技術とLatent Diffusionによる画像生成を組み合わせており、Hugging Face上で簡単に試すことができます。ローカル環境での実行も可能で、日本語入力にも対応していますが、こちらも英語でのプロンプト使用が推奨されています。
コード作成AI
Meta社のCode Llamaは、Llama2をベースに開発されたコード生成AIです。自然言語とプログラムの両方を理解し、コード補完やデバッグ支援、コードの自然言語による解説などができます。対応言語も幅広く、PythonやC++、Java、TypeScript などの主要言語をカバーしています。
また、汎用モデルのほかにPython特化版や指示文対応版もあり、モデルサイズは 7B・13B・34B・70B の中から用途に応じて選択できます。月間ユーザー数が7億人以下であれば商用利用も許可されており、日本語の入力にも対応しています。ただし、現時点では英語のプロンプトのほうが精度は高いです。
StarCoder2は、NVIDIA・ServiceNow・Hugging Faceの3社が共同開発したコード生成AIです。619種類のプログラミング言語に対応しており、ロイヤリティフリーで利用できます。提供されているモデルは、3B(ServiceNow 版)、7B(Hugging Face 版)、15B(NVIDIA 版)の3種類です。コード補完・要約・コード検索などの開発支援タスクで高い精度を誇ります。
また、自社データによるファインチューニングを行うことで、チャットボットなどに応用できる拡張性の高さも魅力です。日本語対応は公式には明示されていませんが、コードコメント程度であれば使える場面もあります。
フレームワーク・実行環境AI
Llama.cppは、Llama系の大規模言語モデル(LLM)を量子化し、GPUがなくても動作する軽量ライブラリです。MITライセンスのもとで提供されており、GitHubからダウンロードして利用・改変することができます。日本語対応は、日本語で学習済みのモデルを使用することで可能です。
LangChainは、PythonやJavaScript、TypeScript で使用できるフレームワークです。LLMと外部ツールを連携させることで、高度な生成AIアプリケーションを短時間で構築できます。こちらも MIT ライセンスで提供されており、商用利用が可能です。接続するLLMが日本語を扱えるものであれば、LangChain上でも多言語対応のアプリケーション開発が可能になります。
オープンソースの生成AIを利用する際の注意点
オープンソースの生成AIは、自由度が高く柔軟に活用できる一方で、ライセンス管理や社内体制を怠ると、想定外のリスクが生じることもあります。以下では、オープンソースの生成AIを利用する際の注意点を解説します。
ライセンスと透明性が複雑
オープンソースの生成AIは、ライセンスには独自の規定が多く、商用利用や再配布の条件が不透明なケースも少なくありません。例えば、Llamaシリーズでは、ユーザー数の上限や表示義務などの制約があります。一方で、Appleの生成AIは特許を含まず、利用範囲に一定の自由度があります。
このように、同じオープンソースを名乗っていても、ライセンスの内容や公開範囲には大きな違いがあります。さらに、トレーニングデータやモデルの構造が非公開のケースもあり、その不透明さが脆弱性や法的リスクの把握が困難です。
また、派生モデルやフォークが重なると、ライセンスの継承関係や修正履歴の管理が複雑になります。その結果、責任の所在が不明になり、利用者が意図しないリスクを負う可能性もあります。
スキル・体制・標準の整備が必要
オープンソースの生成AIを自社で活用するには、モデルの構築やファインチューニング、継続的なメンテナンスを自力で行えるスキルが必要です。また、現場の担当者が独自に導入を進めやすいため、IT部門の統制が届きにくくなる可能性があります。
そのうえ、APIの設計やプロンプトエンジニアリング、エージェントとの連携などの技術の標準化が十分に整備されていないのが現状です。さらに、独立した評価機関が存在しないことも課題と言えます。このため、最終的な判断や継続的な運用管理は、企業自身が担う必要があります。
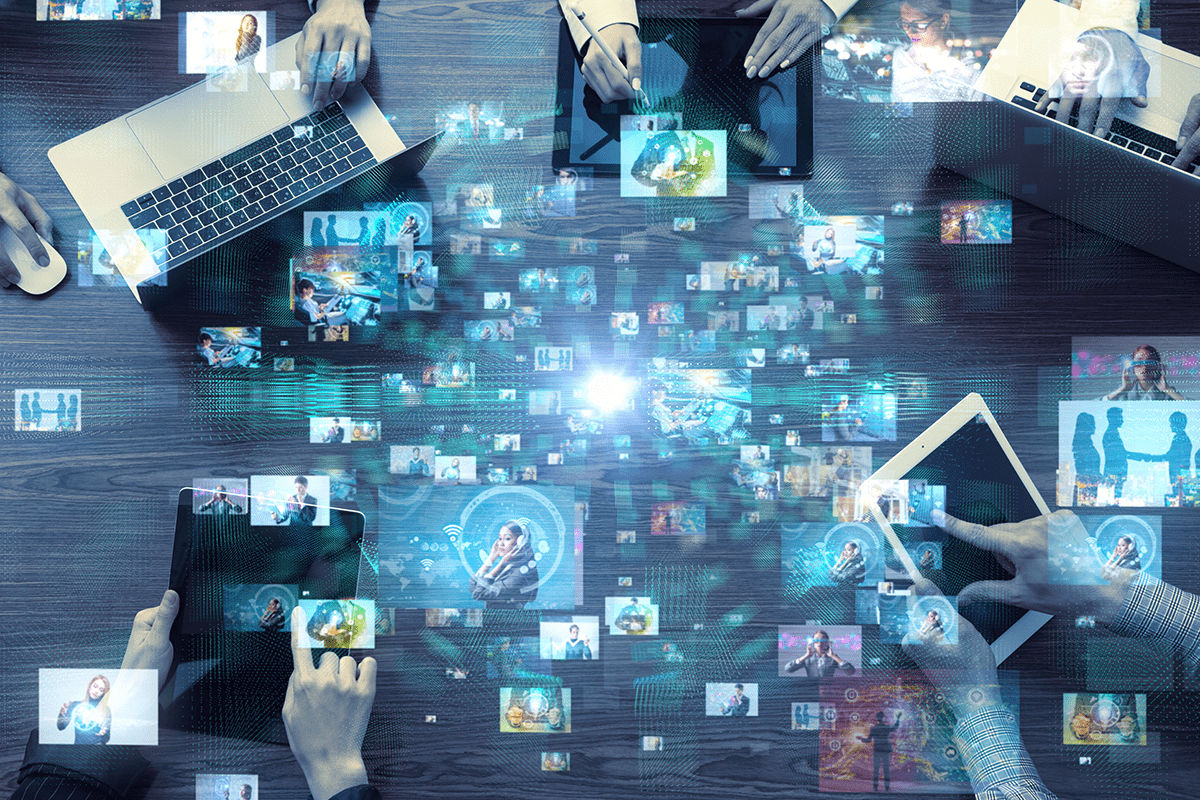
オープンソースの生成AIの導入方法
オープンソースの生成AIを活用するには、いくつかのステップを踏む必要があります。以下に、導入にあたっての基本的な流れを段階ごとにご紹介します。
1.目的とユースケースの明確化
生成AIで解決したい業務を整理し、ゴールを設定します。
2.AIモデルおよびインフラの選定
目的にあったオープンソースの生成AIを比較します。あわせて、GPU構成などインフラの選定を行います。
3.AIモデルの検証の実施
少量データでファインチューニングやRAGを行い、性能とコストを検証します。
4.セキュリティとライセンスチェック
社内規程に沿ってライセンス条項を確認し、機密データの取り扱い基準を決めます。
5.本番環境の構築と運用設計
本番環境を構築し、運用のルールなどを設定します。
6.本稼働とユーザー教育
現場向けにプロンプト設計ガイドやFAQを整備し、継続的なフィードバック体制を作ります。
まとめ
今回は、オープンソースの生成AIの概要や使うメリット、代表的な生成AIツール、利用する際の注意点、導入方法などを解説しました。オープンソースの生成AIは、ライセンス費用がかからず、柔軟なカスタマイズが可能という魅力がある一方で、導入・運用には専門的な知識と社内での管理体制が求められます。
導入にあたっては、ライセンスやセキュリティ要件を正しく理解したうえで、自社の目的に合ったAIモデルやインフラを選定することが重要です。その結果、クラウドへの依存を抑えながら、長期的なコスト削減と業務効率化を実現できます。


