革新的な製品・サービスの開発を行う際に、「プロダクトイノベーション」の考え方が重要になります。しかし、新しいアイデアを生み出すのは容易ではなく、「戦略が思い浮かばない」「どうやって進行すれば良いか分からない」といった意見も多いでしょう。
そこで今回は、プロダクトイノベーションを実現するための4つのアプローチと具体的な方法、実際に社会にイノベーションを起こした事例について紹介します。イノベーションを実現するためのやり方はパターン化されているため、方法が分かればビジネスに活用できます。
プロダクトイノベーションとは?
プロダクトイノベーションという言葉の意味と、社会に及ぼす効果について確認しましょう。
意味:既存商品にない革新的な製品開発
プロダクトイノベーションのプロダクトは「製品」のことで、イノベーションは「創造・革新を通じた社会の変化」と定義されています。これら2つを合わせ、今までにない革新的な製品やサービスを産み出すことをプロダクトイノベーションと呼びます。
プロダクトイノベーションを実現するためには、機能や提供形態、利用場面などさまざまな観点から、既存の製品と差別化できるポイントを洗い出す必要があります。
また、製品そのものの差異は大きくなくても、付随するサービスの形態を変えることで、競合との差別化を図ることもできます。
効果:経済や人々の社会生活に影響
プロダクトイノベーションにより新製品を開発した場合、時として社会を変化させるほどの影響があります。一例として、Appleが開発したiPhoneは、スマートフォンという市場そのものを作り出しました。
また、スマホケースなどの周辺機器やアプリの開発・販売、スマートフォンで視聴できる動画など、幅広い新しいシステムやビジネスを生み出しています。また、iPhoneの登場により、ビジネスの連絡手段や人々のライフスタイルも大きく変化しています。

プロセスイノベーション・マーケットイノベーションとの違い
経済学や経営学の領域では、イノベーションをいくつかの種類に分類しており、プロダクトイノベーションもそのうちの一つです。
他によく言及されるものとして、プロセスイノベーションとマーケットイノベーションがあります。これらの違いについて解説していきます。
プロセスイノベーション:製造・流通の過程の革新
プロセスイノベーションは、製品の製造・流通プロセスにおける革新的な変化を表す言葉です。
例えば、製造業でのロボットによる仕分けの自動化やドローン配達などは、人間の作業を置き換わるプロセスイノベーションと言えます。
製品そのものは大きく変わらなくても、プロセスを変えることで製造・流通を効率化でき、利益を上昇させることができます。
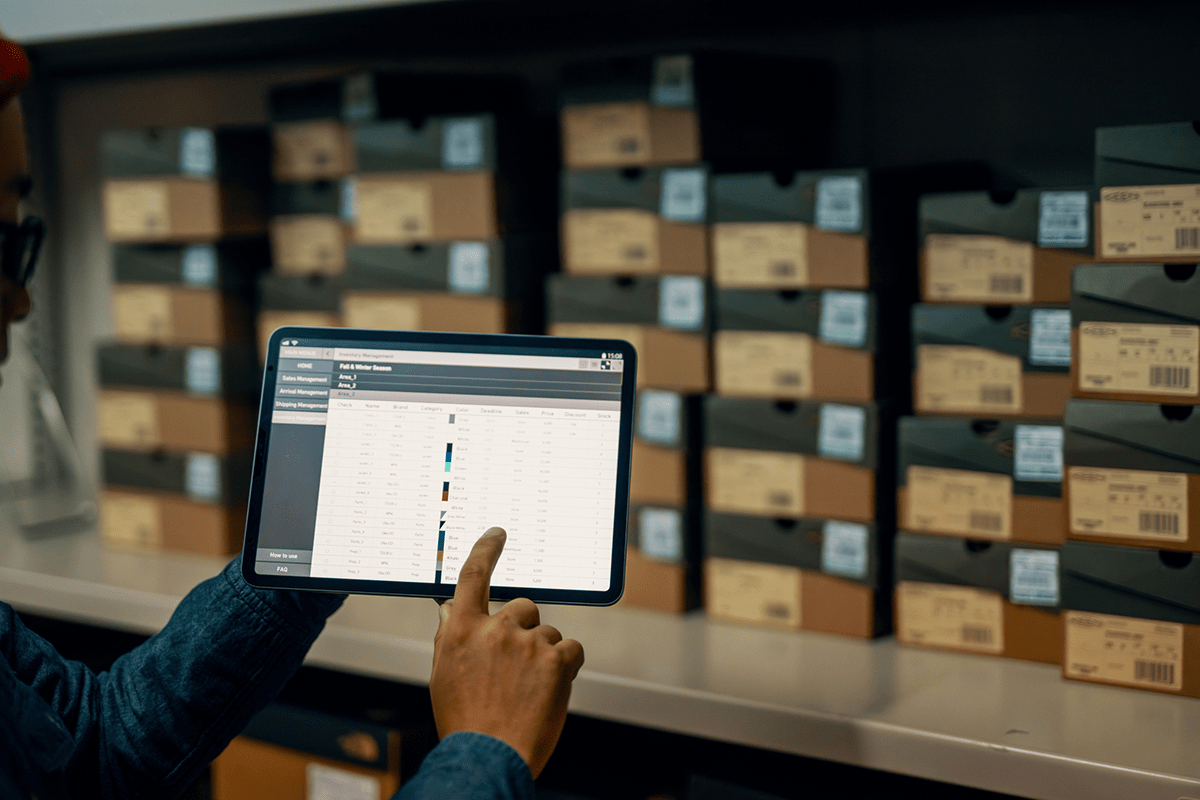
マーケットイノベーション:新市場の開拓
マーケットイノベーションは、製品を提供する市場を新しく生み出すことです。近年の代表例は、音楽や動画コンテンツのサブスクリプションモデルが当てはまります。
今までの音楽や動画は購入・レンタルにより流通していましたが、定額視聴の形態に変革したことで、より手間をかけずに音楽や動画を楽しめるようになりました。サブスクリプションモデルという新しい市場ができたことで、この仕組みを利用したサービスが多く展開されています。
上記のように新しい市場を生み出すことで、利益を上昇させることができます。
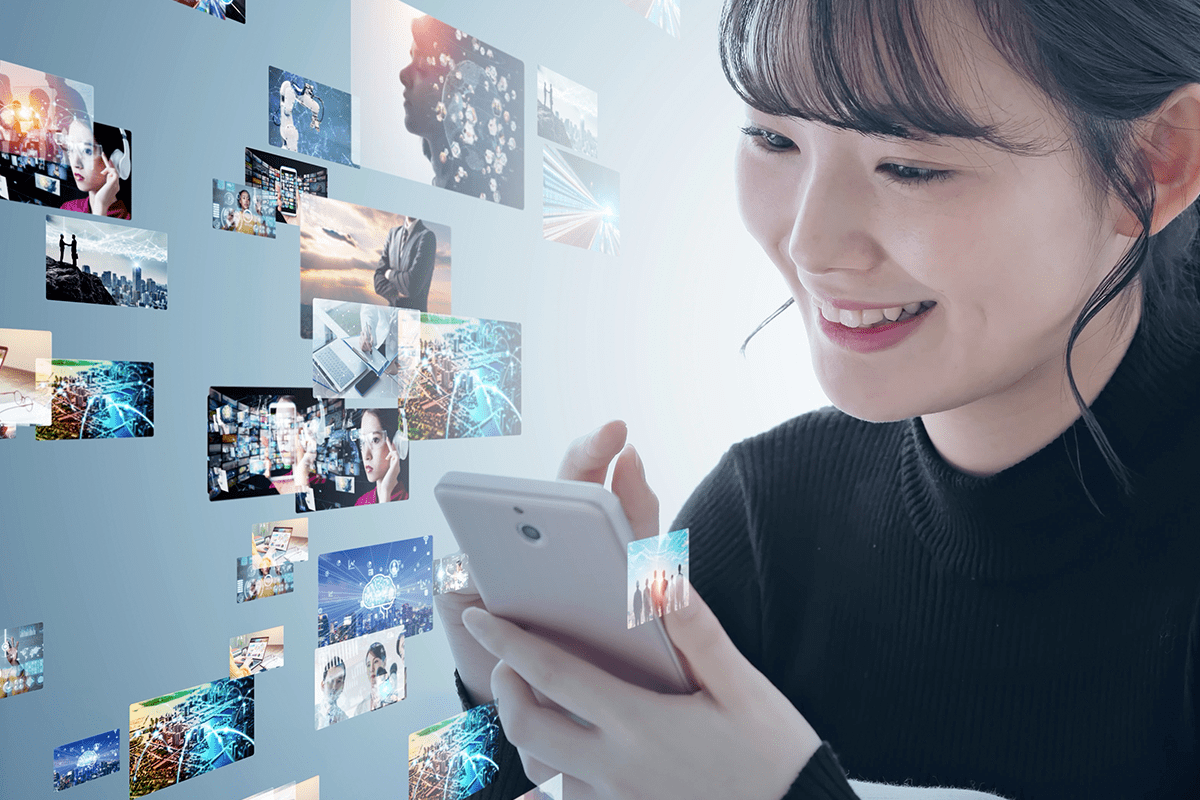
プロダクトイノベーションは大きく分けて2種類
ここからは、プロダクトイノベーションの種類について解説します。
商品イノベーション:他にない新製品の開発
既存の製品とは異なる機能・性能・デザインを持つ製品は、商品イノベーションに該当します。大幅な小型化や軽量化なども、人々のライフスタイルを変革につながっています。
商品イノベーションを進めるには、既存製品の足りない部分や、ユーザーが欲している機能を洗い出すことが重要です。ユーザーが求める製品から逆算することで、新しいアイデアが出てくる可能性が上がります。
素材・部品イノベーション:新機能を実現する素材の開発
今までにない機能・性能・デザインを実現するための素材の開発は、素材・部品イノベーションに該当します。
素材・部品イノベーションの実現も、ユーザーが求めている製品・サービスからの逆算が重要です。「使い慣れている製品を使い続けたいけど、もう1つ便利な機能があればなぁ」「この製品は気に入っているけど、持ちにくいのをどうにかしたい」といった意見を拾い上げ、ユーザーの悩みを解決できる素材や部品を産み出すことで、素材・部品イノベーションを実現できる可能性が高まります。
プロダクトイノベーションの手法・考え方
イノベーションはひらめきだけでなく、継続した企業活動によっても起こすことができます。ここからは、プロダクトイノベーション実現に必要な手法と考え方を見ていきましょう。
技術主導型:テクノロジーの応用・進化
技術主導型のアプローチは、これまで困難であったことを実現するために、製品開発に関する技術の発展を行う手法です。
競合他社よりも優れた技術を用いて、より魅力的な機能、性能を有する製品を開発します。そのためには、継続的な研究開発と、社外の活用できそうな技術を発見し他社よりも先に手に入れるフットワークが必要です。

ニーズ主導型:顧客の望みを実現
ニーズ主導型のアプローチは、顧客の顕在的あるいは潜在的なニーズを発見し、それを満たす製品を開発するものです。以前から身近に存在し、簡単に手に入るものであっても、ちょっとした不満や不便さがあるものです。それらを徹底的なリサーチで明らかにし、解決手段を検討して実現します。
身近な例では、「急須で入れて飲むもの」「水と同じように無料で飲めるもの」というイメージがあった「緑茶」を屋外でいつでも飲めるようにした「缶入り緑茶」の発売 (1985年) があります。さらに、「一度に飲みきれないので蓋をしたい」というニーズを踏まえて「ペットボトル入り緑茶」への改良 (1990年) へと繋がり、現在に至っています。

類似品型:既存製品に付加価値を加えて改良
類似品型のアプローチは、すでに市場に存在する競合製品を研究し、よく似た外観、機能はそのままに、弱点を改良した製品を開発するというものです。
また、優れた素材、部品を開発することで、小型化、高性能化、コストダウンを実現し、付加価値の向上も図ります。高度経済成長期までの日本企業の代表的な戦略でした。
商品コンセプト型:サービス提供側のアイデアを先行
商品コンセプト型のアプローチは、メーカーの思い描く利用シーンや変化した社会の姿 (コンセプト) が先にあり、それを実現するための製品を開発して販売するというものです。
コンセプトに共感を得られれば、まさに社会を変えるほどのヒットが望めますが、顧客のニーズと合致しない場合、失敗してしまうこともあります。また、素材、部品の研究開発が難航し、コンセプトを実現できないままフェードアウトするパターンもあります。
プロダクトイノベーションの成功事例
最後に、実際に革新的な製品を開発し社会に影響を及ぼした、プロダクトイノベーションの事例を紹介します。
WALKMAN(ウォークマン)
日本企業によるイノベーションの最も有名な事例として、ソニーのウォークマンがあります。
「好きな音楽を、いつでもどこでもステレオの高音質で聞きたい」という消費者 (ソニー経営者自身) のニーズをもとに、既存のモノラルテープレコーダーを改良し、再生専用の携帯型音楽プレイヤーを生み出しました。
このコンセプトは世界中で受け入れられ、大ヒットしました。プロダクトイノベーションの手法では、ニーズ主導型と類似品型を組み合わせたアプローチと言えるでしょう。
ウォークマンが示した「好きな音楽をいつでもどこでも」というライフスタイルは、現在では完全に定着し、当たり前の風景となっています。

パソコン・スマホ用メガネ
メガネは700年以上前から存在し、レンズで視力を矯正することにいたっては2000年以上の歴史があります。そのため、市場は完全に開拓しつくされたと考えられていました。
しかし、メガネの役割を「目を保護する」と再定義したことで、パソコンやスマートフォンのディスプレイから発せられ、眼精疲労などを引き起こすとされるブルーライトから目を守るためのメガネ、という新しい製品が生まれました。
視力に問題のない人にも、ブルーライトをカットして目を保護するという価値を訴求したことで、新しい市場を開拓した事例です。類似品型のアプローチが成功したパターンと言えるでしょう。
ジェルボール
洗濯用洗剤におけるイノベーションの事例として、P&Gが開発したジェルボール型洗剤があります。長い間、洗剤は利用者がスプーンで計量して使用する必要がありました。
また、計量や詰め替えの際に洗剤をこぼしてしまうこともあり、消費者は不便を感じていました。液体洗剤にも手が汚れるなどの不満がありました。それらを解決するための手段として、1回分の洗剤を、手が汚れずに投入できるフィルムに包んだジェルボールが開発されました。
これは、洗濯をより効率的に行いたいというニーズを捉え、またそれを実現するために破れにくいが水には溶けやすい特殊なフィルムを開発した、ニーズ主導型と素材・部品イノベーションの組み合わせと言えるでしょう。

まとめ
この記事では、革新的な製品・サービスの開発を意味する「プロダクトイノベーション」について解説しました。
世界を変える製品を作る、というのは困難なことではありますが、ニーズ主導型や類似品型など、すぐにでも着手できるアプローチもあります。この記事を参考に、ぜひプロダクトイノベーションの実現に向けて取り組んでみてください。


