Webサイトやアプリ、システム、ネットワークなどの運営に欠かせない存在であるサーバーですが、サーバー障害が起きると、社内の業務やサービス利用者に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
そのため、サーバーを管理する担当者にとって、サーバー障害に関する知識は欠かせません。サーバー障害の知識があれば、障害が発生した際の迅速な対応が可能になるだけでなく、事前にトラブルを回避することにもつながります。
そこで今回は、サーバー障害の意味や発生する原因、対応方法、未然に防ぐ方法などについて解説します。本記事を参考にして、サーバー障害の予防や対応にお役立てください。
サーバー障害とは?障害によって発生する影響
サーバー障害が発生すると、社内の業務効率の低下以外にも顧客や関係機関からの信頼を失うなど、企業に深刻なダメージを与える可能性があります。
ここからは、サーバー障害の意味や障害によって発生する影響について解説します。
サーバー機器・システムが停止すること
サーバー障害とは、サービスや情報、機能を提供するサーバーに問題が発生し、機器やシステムが正常に動作しなくなる状態を指します。
サーバー障害が発生すると、企業の基幹システムやWebサービスが利用できなくなり、大きな被害を受ける可能性があります。そのため、サーバー障害への対策は、企業にとって欠かせない課題となっています。
一方、サーバーが完全に停止する状態は「サーバーダウン」と呼ばれ、こちらも対策が必要です。
詳しくは「サーバーダウンの原因は?対処方法や未然に防ぐ対処法を解説」をご覧ください。
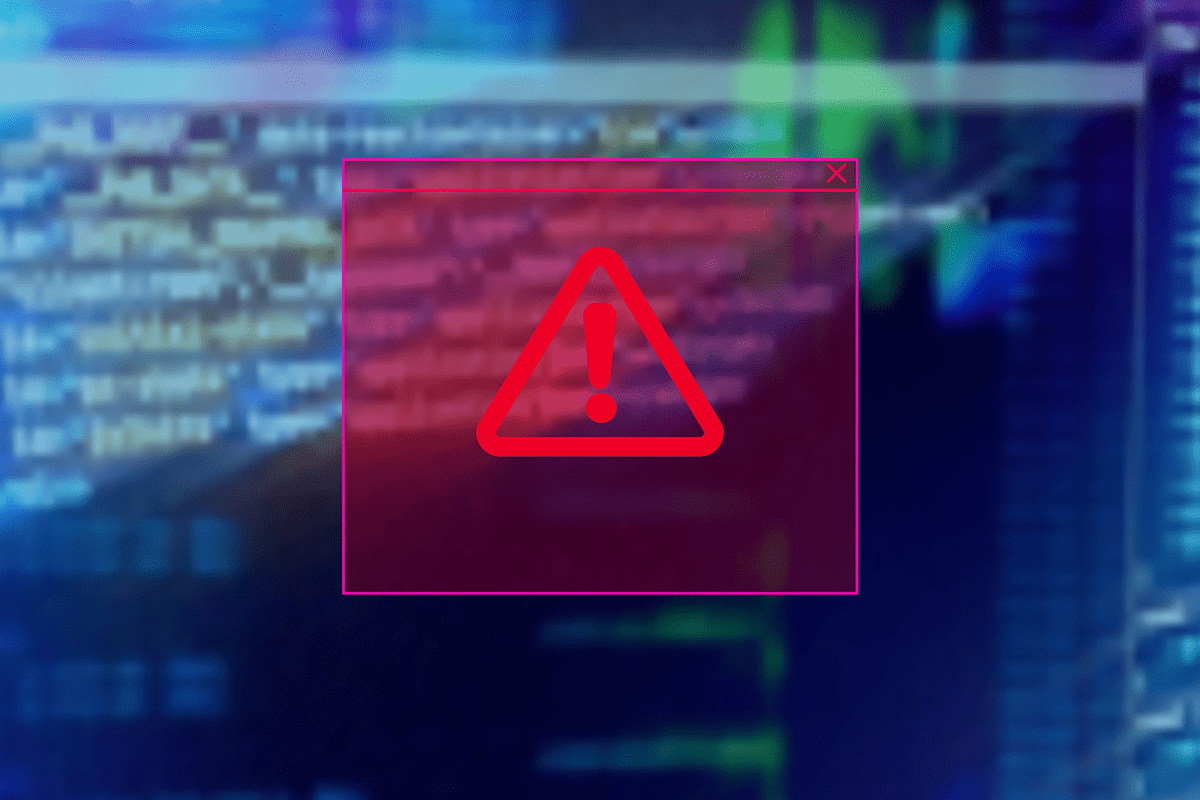
サーバー障害は顧客・関係機関への信頼を失う
サーバー障害が発生すると、顧客や関係機関からの信頼が損なわれます。例えば、ネットワーク環境に問題が生じると、決済システムが利用できなくなり、売上機会を失うことも考えられます。
その結果、会社のブランド力が低下する可能性もあります。また、オペレーションの混乱によって、取引先から損害賠償や補償を求められるリスクも考えられます。
サーバー障害が発生する内部的な原因
サーバー障害が発生する原因は、内部的原因と外部的原因に分けられます。まずは以下の内部的原因について解説します。
ハードウェアの故障
サーバー障害の内部的な原因のひとつが、ハードウェアの故障です。サーバーは基本的に24時間稼働しているので、発熱で電子部品が徐々に消耗し、突然の機能不全を引き起こす場合があります。
また、メモリやSSDなどのパーツが寿命を迎えると、システム全体が停止に追い込まれていきます。
システム・ソフトウェアの不具合
サーバー障害は、複数のソフトウェアが連携して動作する中で、一部のプログラムに不具合が生じることで発生します。また、システムのリソースが不足することで、サーバー障害につながることもあります。
特にOSの更新作業やメンテナンス作業の直後に、予期せぬエラーが起きやすい傾向です。

人為的なエラー
作業状のケアレスミスや情報共有不足が原因で、サーバー障害につながるケースは少なくありません。例えば、人為的なエラーとして、必要なファイルを誤って削除したり破損させたりする操作や、パーティション設定のミスが挙げられます。
サーバー障害が発生する外部的な原因
次に、サーバー障害の外部的な原因の内、代表的な例を解説します。
アクセス集中
アクセスが集中するとサーバーに過剰な負荷がかかり、処理が追いつかなくなる場合があります。 その結果、サーバー障害が発生するケースは少なくありません。サーバー障害が発生すると、ユーザーはサービスを利用できなくなり、運営側からしても、顧客の減少や機会損失に繋がります。
外部からのサイバー攻撃
サイバー攻撃には不正アクセスやデータ改ざん、破壊、ウイルスなど、さまざまな手法があります。これらのサイバー攻撃は年々巧妙化しており、セキュリティを突破する危険性も年々高まります。その結果、外部からの悪質なアクセスにより、サーバー障害が発生することもあります。
また、大量のアクセスでサーバーに過剰な負荷をかけるDDoS攻撃によって、サーバー障害が引き起こされるケースも多いです。
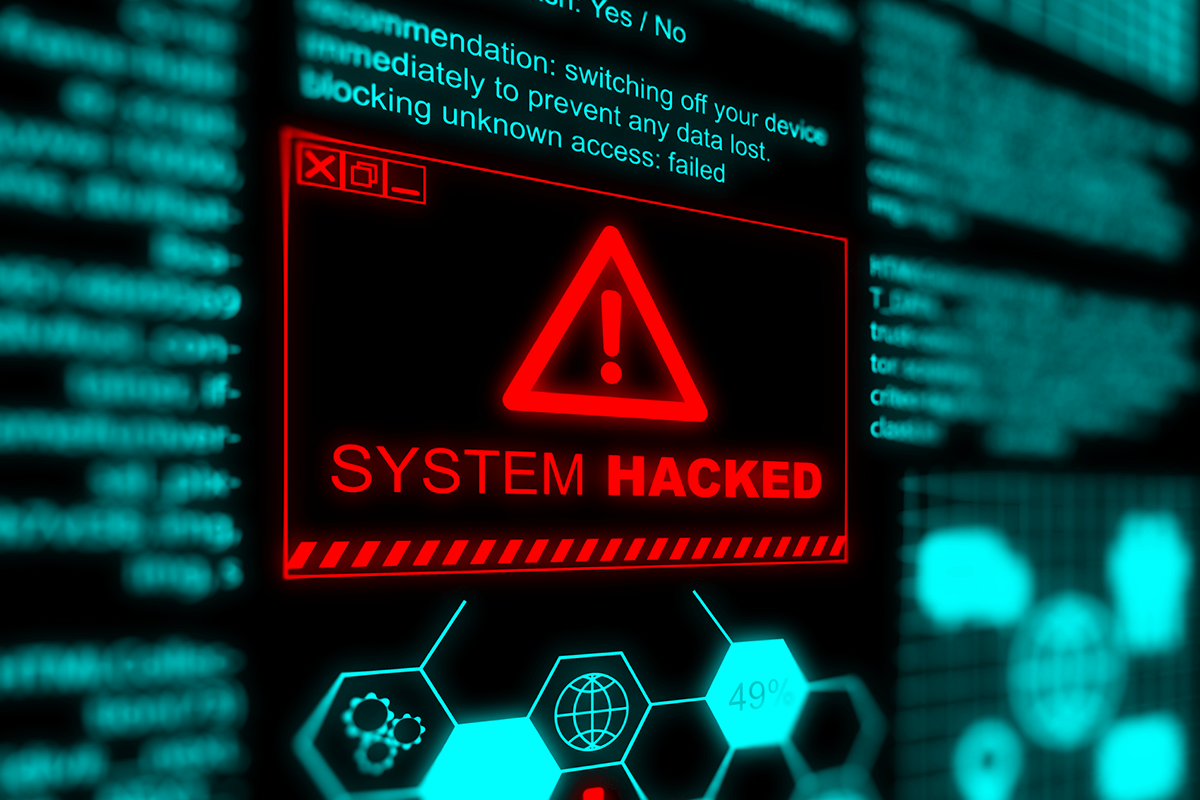
自然災害による損壊
地震や落雷などの自然災害によって、サーバーが設置されている施設の損壊が起きることがあります。それにより、サーバー障害が起きることもあります。
ただし、多くのデータセンターは自然災害による被害を受けないように対策されています。そのため、自然災害によるサーバー障害は少ないといえます。
サーバー障害が起こったら?すぐにとるべき対応
サーバー障害が発生したら、適切な対応をとることが重要です。ここからは、サーバー障害時にとるべき対応について解説します。
サーバー障害によって出る影響を特定する
サーバー障害が発生した際に最初に行うべきことは、サーバー障害による影響の程度や範囲を特定することです。サーバー障害の影響度合いによって、一時停止か部分利用かの選択も分かれていきます。
そして、利用者への対応方針や代替手段の検討も、状況に応じて臨機応変に判断していく必要があります。また、レンタルサーバーなど外部のサーバーを利用している場合は、管理会社のホームページなどでサーバー障害かどうかを確認することが重要です。
関係者・各部署に報告する
サーバー障害の発生を確認した段階で、まず社内外の関係者へ現状を速やかに報告していきます。障害の規模や復旧の見込みなど、状況が明らかになり次第、速やかに情報を共有することが重要です。 外部サーバーを利用している場合は、担当窓口へ即座に連絡を入れ、復旧対応を要請します。
サーバー障害の原因を特定する
サーバー障害が発生した場合は、ハードウェアやOS、ネットワーク、アプリケーションなど、レイヤーごとに不具合を調査します。DNSサーバーの設定ミスやドメインの期限切れも、サービス停止の原因となる可能性があります。
さらに、ネットワーク障害の可能性も考えられるため、通信経路の接続状態を確認し、問題箇所を特定することが有効です。また、サーバー管理会社の担当者から連絡があった場合は、その指示に従って原因の特定を進めましょう。
発生箇所を見極めた上で復旧作業を行う
問題の発生箇所を見極めた上で、該当レイヤーに対して復旧作業を進めていきます。サーバー障害の状況については、管理者から社内の関連部署へ随時、最新の情報を共有します。
外部のサーバー管理会社に委託している環境では、担当会社からの復旧完了連絡を待つようにします。トラブル発生から1時間が経過した場合、深刻な事態に備えてバックアップ体制を整えましょう。 システムダウンから5時間以上が経過した際には、バックアップ環境への切り替えを検討するタイミングとなります。
再発防止策を検討し実施する
サーバー障害が復旧した後は、再発防止策を検討し、実施することが重要です。再発防止策を講じなければ、同じ原因で再びサーバー障害が発生する可能性があります。 特に、アクセス集中が原因の場合は、再発のリスクが高くなります。自社で対応が難しい場合は、専門業者に依頼するのも有効です。
また、外部サーバーを利用している場合は、管理会社の切り替えを検討するといいでしょう。
サーバー障害の影響を未然に防ぐための方法
サーバー障害が発生した際に、影響を少なくすることが重要です。ここからは、サーバー障害の影響を未然に防ぐための方法について解説します。
データのバックアップをとっておく
サーバー障害により、保存されているデータが失われてしまうリスクが存在します。万が一の事態に備えて、システム設定やデータをあらかじめバックアップに保存しておきましょう。
日頃からバックアップを実施していれば、問題が発生した際にもシステムを速やかに元の状態に戻せます。
予備のサーバーを用意しておく
予備サーバーを準備しておくことで、サーバー障害が発生しても、業務への影響を最小限に抑えつつ、復旧作業を進めることができます。
ITインフラの運用管理において、万全な体制を整える仕組みは「冗長化」と呼ばれています。メインのサーバーに不具合が見つかった際も、予備サーバーへの切り替えにより、システムの停止を防げます。
監視システムを導入する
監視システムを導入することで、サーバー障害の予兆を自動的に検出し、異常の発生を即座に把握できます。これにより、サーバー障害のリスクを最小限に抑え、問題が発生した際にもスピーディーな復旧が期待できます。
さらに、24時間稼働する自動監視プログラムがサーバーの状態を常時分析するため、異常の早期発見から対策までをスムーズに進めることが可能です。
ロードバランサーを導入する
ロードバランサーを活用すると、サーバー障害のリスクを軽減できます。ロードバランサーは、複数のサーバーにアクセスの負荷を分散させる役割を果たします。
アクセスが一時的に集中しても、サーバーへの負担を最小限に抑えることが可能です。結果として、システムの安定稼働が期待でき、サーバー障害を防ぎやすくなります。
障害対応方法を社内で共有する
サーバー障害への対応方法を社内で共有することは欠かせません。サーバー障害は予測できないタイミングで起こり、管理者が不在のケースも考えられます。
そのため、緊急時の対応マニュアルをあらかじめ整備しておくことで、トラブルが発生した際の業務への影響を減らせます。組織全体で情報を共有し、迅速に対応できる体制を整えることが、安定した運用につながります。
まとめ
今回の記事では、サーバー障害の意味や発生する原因、対応方法、未然に防ぐ方法などについて解説しました。サーバー障害は、機器やシステムの正常な動作が停止する状態を指し、企業活動に深刻な影響を及ぼします。
原因は内部的要因と外部的要因に分類され、内部では機器の故障やソフトウェアの不具合、人為的ミスが挙げられます。外部では、アクセス集中やサイバー攻撃、自然災害などが該当します。
予防策として、データのバックアップや予備サーバーの設置、監視システムの導入が効果的です。さらに、ロードバランサーによる負荷分散や、社内での対応手順の共有も重要な取り組みとなります。
これらの対策を組み合わせることで、サーバー障害のリスクを最小限に抑え、発生時の影響を軽減できます。


