システム開発や運用にはサーバーOSの知識が必要ですが、仕組みが複雑なので「理解が難しい」と感じる方は多いかと思います。また、他の人にサーバーOSを説明する際に「具体的な説明ができない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、サーバーOSの概要や種類、選び方のポイント、導入手順、利用する際の注意点などについて解説します。サーバーOSの導入や運用をスムーズに進めるための参考として、ぜひご活用ください。
サーバーOSとは【サーバー専用のOS】
サーバーOSとは、サーバー専用に設計されたOS(オペレーティングシステム)のことで、主に「Windows」「UNIX」「Linux」の3種類があります。
これらのOSは、複数のパソコンから同時接続できるように設計されており、セキュリティ面でも高い信頼性を備えています。また、デスクトップ向けのOSと比べ、長時間の稼働やシステムの安定性を重視して設計されています。
クライアントOSとの違い:サービス提供に優れているOS
クライアントOSには、画像処理や音声出力などのアプリケーションを快適に動作させる機能が備わっています。グラフィカルなサービスを利用者に提供できるため、日常的な作業に適しています。
これに対してサーバーOSは、多くのユーザーからのアクセスに応答しながら、長時間の安定稼働に適しています。
ミドルウェアとは【中間処理を行うソフトウェア】
ミドルウェアとは、クライアントOSとアプリケーションをつなぐ中間的な処理を担うソフトウェアです。OSとアプリケーションの間に位置して、双方の機能をサポートする役割を備えています。
ミドルウェアが存在することで、OSとアプリケーション間の動作がスムーズになり、より高度な機能も実現できます。
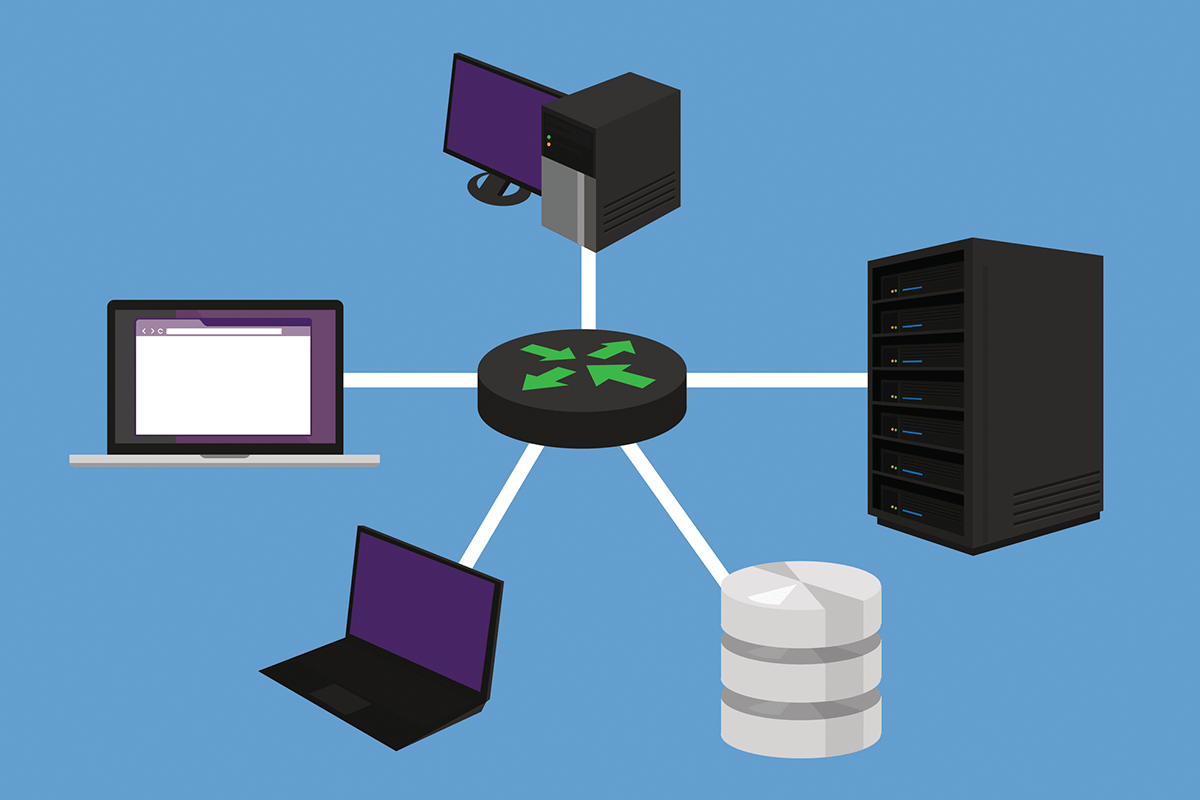
サーバーOSの種類とそれぞれの特徴
冒頭でもお伝えした通り、サーバーOSは主に「Windows系」「UNIX系」「Linux系」の3種類に分類されます。それぞれのOSは独自の特徴を持ち、それを正しく理解することで、効率的かつ効果的な運用が可能となります。
ここからは、各サーバーOSの種類とその特徴について詳しく解説します。
Windows系:操作が簡単
Windows系のサーバーOSは、クライアントOSであるWindowsと操作画面が似ているため、直感的で使いやすい点が特徴です。特に、Windowsに慣れているユーザーにとっては、学習コストを抑えながら運用を始めることができます。
クライアントOSがWindowsの場合、Windows系サーバーOSとの相性が良く、システム全体の連携がスムーズになります。
また、Windows系のサーバーOSには、「Active Directory」という独自の管理システムが搭載されています。これにより、ユーザー管理や設定変更を一括で効率的に行うことが可能です。
なお、Windows系のサーバーOSを利用する場合には、ライセンス料が発生します。このライセンス料は、サーバーに同時接続するユーザー数に応じて支払う必要があります。その結果、費用が高くなりやすい点がデメリットです。
UNIX系:セキュリティに優れている
UNIX系のサーバーOSは、セキュリティ性や安定性に優れている点が大きな特徴です。さらに、スペックの低い機種でも軽快に動作するため、多くの企業で採用されています。
一方で、操作は主にキーボードを使ったコマンド入力で行うため、専門的な知識が必要です。また、サポートが有料である点もデメリットといえます。
Linux系:低コストで運用可能
Linux系のサーバーOSは、低コストで運用できる点が最大の特徴です。また、オープンソースであるため、さまざまな種類が存在し、用途や環境に応じた選択が可能です。さらに、USBメモリを挿入するだけで利用できる簡易的なものもあり、手軽さも魅力のひとつです。
一方で、Linux系のサーバーOSには、マニュアルが十分に整備されていない点や、日本語化が進んでいない点がデメリットとして挙げられます。また、対応していないソフトウェアが多いことも課題で、UNIX系と同様に、運用には専門的な知識が求められる点もデメリットと言えます。
Linuxについて詳しくは、「Linuxでサーバー構築したい人必見!使用方法やメリットを解説」をご覧ください。
サーバーOSの選び方・確認ポイント
サーバーOSを選ぶ際は、以下のポイントを確認する必要があります。
ここからは、それぞれのサーバーOSの選び方・確認ポイントについて解説します。
また、Webサーバー構築やAWSサーバー構築について詳しくは
「Webサーバーを構築・立ち上げるメリットは?種類から選び方まで解説」
「AWSサーバーの構築方法は?図解で分かりやすく解説」
をご覧ください。
業務機能が動作するか
サーバーOSを含むシステムを構築する際には、業務機能を最優先に考える必要があります。
例えば、特定の業務アプリケーションが特定のOSにしか対応していない場合、そのOSしか採用できない状況になることがあります。また、開発部門が得意とするプログラミング言語や実行環境が特定のOSに依存している場合も、選択肢が限定される要因となります。
サポートが提供されるか
障害発生時には、一貫したサポート体制が整っていることが重要です。システムの安定運用や障害への迅速な対応には、メーカーによる専門的な支援が大きな助けとなります。メーカーのサポートがあることで、ユーザー企業がリスクや責任を単独で負う必要がなくなり、効率的かつ効果的に問題を解決することが可能です。
また、メーカーが選定された場合、ハードウェアやOSもそのメーカー専用のものが採用されることがあります。このような環境下では、サーバーOSを変更することが容易ではなく、変更には慎重な判断と対応が求められます。
既存の運用に適応するか
サーバーOSが既存の運用環境に適合するかどうかは、必ず確認すべき重要なポイントです。近年では、運用をシンプルにし、運用コストの削減を目指す手法が増えています。
そのような場合、既存環境と同じOSを採用することが優先される傾向があります。同じOSを使用することで、システム統合の手間や追加の学習コストを抑えられるため、効率的な運用が可能となります。
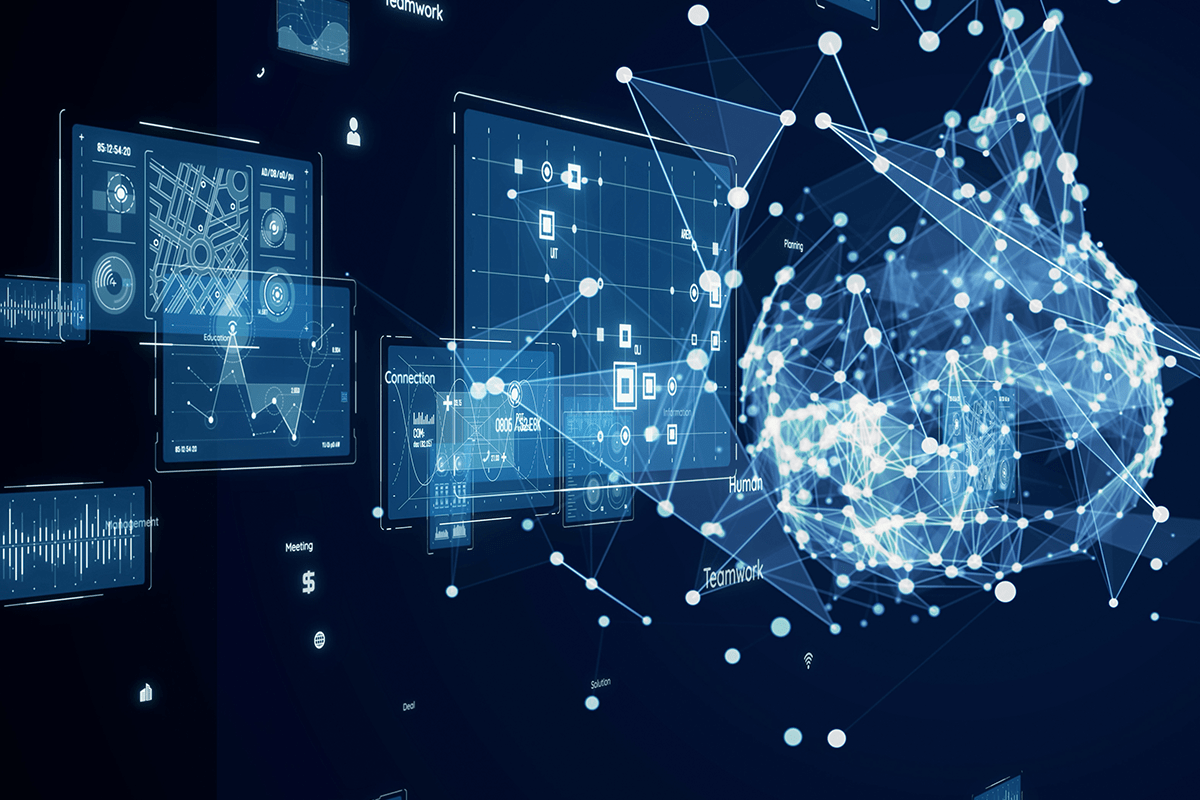
サーバーOSを導入する手順
サーバーOSを導入する際の手順は、Windows系サーバーとUNIX系サーバーで異なります。それぞれの特徴に応じた導入手順が必要です。
Windows系サーバーの場合
UNIX系サーバーの場合
サーバーOSを利用する際の注意点
サーバーOSを利用する際には、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。ここからは、サーバーOSを利用する際の注意点について解説します。
技術者を確保しておく
サーバーOSを利用する際には、専門の技術者を確保することが重要です。サーバーOSは高度に専門化された複雑な構造を持っており、十分な知識がないと操作や管理ができません。
サーバーOSを導入する際には、運用や管理に対応できる技術者を事前に確保して進めることが、安全かつ適切な方法です。専門知識を持つ技術者がいることで、スムーズな導入と運用が可能になります。

利用にお金がかかるものもある
Windows系やUNIX系のサーバーOSは、サポート費用やライセンス料が有料である場合が一般的です。一方で、Linux系のサーバーOSはライセンス料が発生しないため、低コストで利用できます。
サーバーOSの導入を検討する際には、これらのコストを事前に調べておき、適切な予算管理を行いましょう。
対応していないソフトウェアもある
サーバーOSを利用する際には、動作しないソフトウェアが存在する可能性を考慮する必要があります。特に、パソコンのOSを別のものに切り替える場合は、動作環境の違いに注意が必要です。
新しいOSに移行することで、これまで利用していたソフトウェアが正常に動作しなくなるケースもあります。そのため、OSを採用する前に、業務で使用するソフトウェアの互換性を事前に確認することが重要です。
また、スムーズな移行を実現するためには、段階的な移行計画の策定が求められます。
まとめ
今回の記事では、サーバーOSの概要や種類、選び方のポイント、導入手順、利用する際の注意点などについて解説しました。サーバーOSは、サーバー専用に設計されたOSで、「Windows系」「UNIX系」「Linux系」の3種類に大別されます。
Windows系は操作が直感的で使いやすく、Active Directoryによる管理機能が特徴ですが、ライセンス料が高額になりやすい傾向があります。UNIX系はセキュリティと安定性に優れ、低スペックでも動作しますが、専門知識が必要です。Linux系は低コストで運用でき、用途に応じた選択が可能ですが、対応ソフトが限られます。
サーバーOSの導入時には業務機能の動作確認、サポート体制、既存環境との適合性が重要なポイントとなります。また、専門技術者の確保や、ライセンス料などの費用確認、ソフトウェアの互換性チェックも必要です。


