クラウドインフラとは、物理的なサーバーやネットワーク機器を仮想化技術で統合し、インターネット経由で利用できる基盤システムです。DXの進展に伴い、多くの企業がクラウドインフラの導入を検討しています。
しかし、「クラウドインフラの概要を知りたい」「自社に最適なクラウドインフラのモデルが知りたい」などの疑問を持つ方も少なくありません。
そこで今回は、クラウドインフラの概要や構成要素、SaaS・PaaS・IaaSとの違い、メリット・デメリット、成功事例などを解説します。
クラウドインフラとは?【ハードウェアとソフトウェアの基盤】
クラウドインフラとは、サーバーやネットワーク機器、ストレージ、仮想化ソフトウェアなどで構成される「ハードウェアとソフトウェアの基盤」のことです。ユーザーは、サーバーやストレージなどのクラウドサービスをインターネット経由で利用できます。
クラウドインフラを導入すると、自社で機器を購入・管理する必要がなくなり、初期投資や保守にかかる負担を抑えることが可能です。多くのクラウドサービスではオンデマンド型(利用分の料金が発生する仕組み)が採用されており、必要なときに必要な分だけリソースを利用できます。これにより、ビジネスの変化に応じた柔軟な対応がしやすくなります。
また、クラウドプロバイダー(クラウドサービスの提供会社)が高度なセキュリティ対策(暗号化・アクセス制御・常時監視など)を提供しているので、安全な運用環境を確保できます。
一方で、クラウドの内部構成が見えにくく、設定ミスがトラブルにつながる恐れもあります。リスクを避けるには、利用状況を把握できる可視化ツールの導入や、明確な運用ルールの策定が欠かせません。
ITインフラ全体について詳しくは、関連記事「ITインフラとは?役割や構築・運用の流れを注意点を含め解説」をご覧ください。
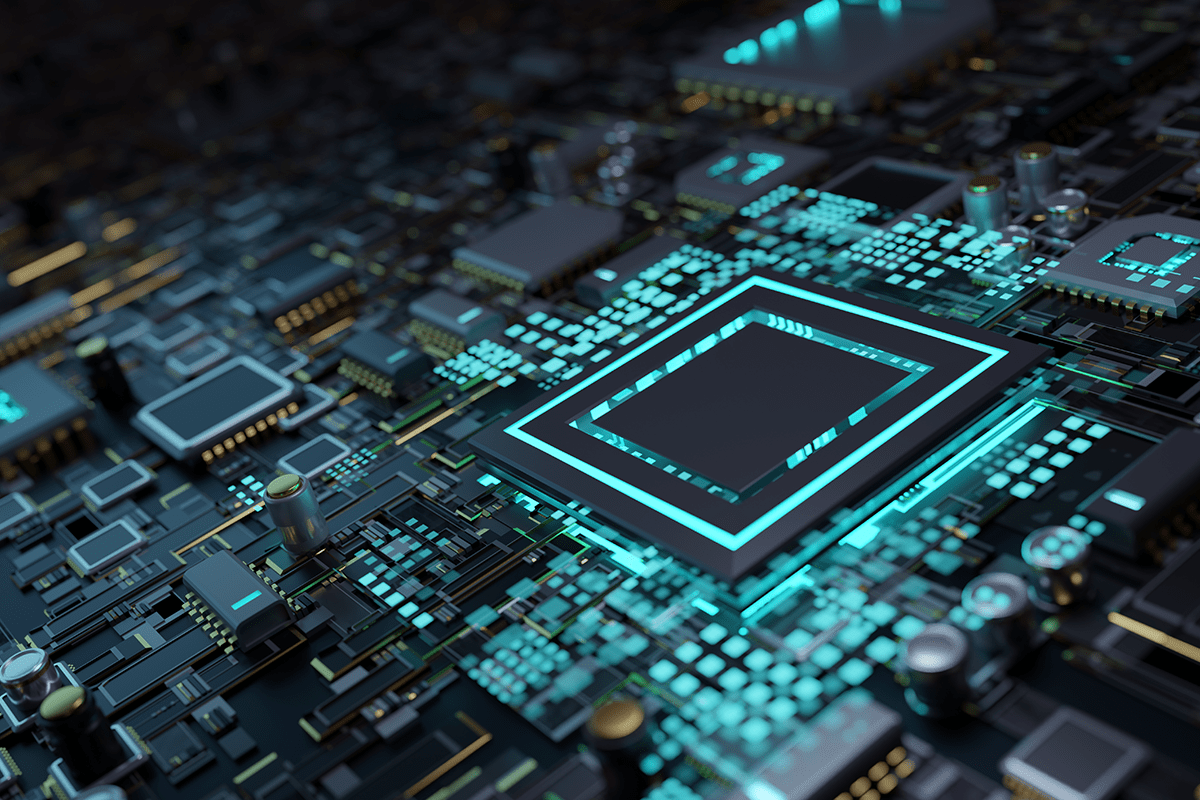
仕組み:物理リソースを抽象化して提供
クラウドインフラでは、仮想化技術で物理リソース(サーバーやストレージなど)をまとめ、ひとつの仮想リソースプールとして利用できる仕組みです。
使用する企業は、クラウドプロバイダーから仮想リソースプールを割り当てられ、必要に応じてリソースを柔軟に増減できます。設備面の制約を気にせずシステムを拡張できる点は、クラウドインフラ特有の利点です。
また、アプリケーションやデータをクラウド上に置くことで、クラウドプロバイダーによる専門的なバックアップや保守対応が受けられ、耐障害性やセキュリティの向上にもつながります。その結果、企業は業務リスクを抑えつつ可用性の高い環境を確保でき、より安定した運用が可能となります。
クラウドコンピューティングとの違い:機能やサービスを指す
クラウドインフラが仮想化の基盤なのに対し、クラウドコンピューティングは、クラウドインフラの基盤上で動作する、処理機能やストレージ、アプリケーションなどのサービスを指します。
SaaS・PaaS・IaaSといった提供形態も、クラウドインフラの設備と仮想化技術の上で成り立ちます。クラウドコンピューティングはクラウドインフラを前提として構築されている仕組みと言えます。
クラウドアーキテクチャとの違い:設計や構築の方法論を指す
クラウドアーキテクチャとは、クラウドインフラを使って、サービスをどのように設計・構築するかを考える方法のことです。マイクロサービスやAPIゲートウェイ、コンテナ基盤などを組み合わせることで、利用者の増加に対応しやすく、トラブルにも強い仕組みを作成できます。
クラウドインフラが「土台」の役割なのに対して、クラウドアーキテクチャは「土台の上にどのような仕組みをどう組み立てるか」という「設計図」の役割を持ちます。システム開発では、アーキテクチャを活用することで、システムを素早く改善・更新できたり、自動でリソースの調整ができたりと、効率よくサービスを運用できます。
クラウドインフラの構成要素
ここからは、クラウドインフラを支える主な4つの要素、「サーバー」「ネットワーク」「ストレージ」「ソフトウェア」を解説します。
サーバー
クラウドインフラに使われているサーバーには、多コアCPUや大容量メモリが搭載されており、大規模な処理にも対応できる設計になっています。これらを高速ネットワークで接続し分散処理を行うことで、高い安定性や拡張性、可用性が確保されています。
また、仮想化技術を活用すれば、1台の物理サーバー上に複数の仮想サーバーを構築できます。仮想サーバーはソフトウェアで一括管理できるので、運用の負担を減らしながら効率的なシステム構成を保てます。
サーバーについてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事も参考にしてみてください。
ネットワーク
クラウドネットワークは、サーバーやストレージ、アプリケーションを高速なネットワークで結び付け、大規模システムのように機能させる技術です。
クラウドプロバイダーは、ロードバランサー(アクセスを分散させて負荷を抑える装置)やネットワークスイッチ(複数のデバイスを接続できるネットワーク機器)などのソフトウェアやハードウェアを駆使し、通信経路を常に最適な状態に調整することができます。
さらに、複数のサーバーを仮想環境で統合し、大きなネットワークとして構成することで、リソースの効率的な共有が可能です。このような仕組みにより、企業はビジネスの成長に応じて、無理なくシステムの規模を拡大していくことができます。
ストレージ
クラウドストレージは、クラウド上に用意されたデータの保存領域です。物理的なストレージ機器を持つ必要がなく、保守の手間やコストを削減できます。さらに、インターネットが使える環境であれば、どこからでもアクセスできるので、リモートワークや拠点が複数ある場合でも使いやすい点が特徴です。
ファイルはURLで簡単に共有でき、複数人での作業もスムーズに行えます。容量や保存先(リージョン)も必要に応じて柔軟に追加・変更でき、用途に合わせてストレージを選べる点も便利です。
ソフトウェア
クラウドインフラを構成する上で欠かせないのが、ソフトウェアです。ユーザーは、Webブラウザや専用の管理画面(GUI)を使い、仮想マシンの作成や設定、リソースの追加・削除などを簡単に操作できます。
こうした操作が可能なのは、仮想化技術によってハードウェアの機能がソフトウェア上で扱えるようになっているからです。物理的なサーバーやストレージ、メモリといったリソースは、仮想的に再構成され、必要に応じて柔軟に使える形で提供されます。
その仕組みの中心にあるのが「ハイパーバイザー」と呼ばれるソフトウェアです。ハイパーバイザーは、物理サーバーにあるリソースを取りまとめ、複数の仮想マシンに効率よく割り振る役割を担います。これにより、1台の物理サーバーでも、複数のシステムを同時に動かすことが可能になります。
クラウドインフラのサービスモデル
クラウドインフラには、目的や利用方法に応じたさまざまなサービスモデルがあります。どのモデルが自社のニーズに合っているかを見極めることは、クラウド導入を成功させるための重要なポイントです。ここからは、代表的な3つのサービスモデルである「SaaS」「PaaS」「IaaS」について、それぞれの特徴を解説します。
SaaS:ソフトウェアをクラウド経由で提供
SaaS(Software as a Service)は、ソフトウェアをインターネット経由で利用できるクラウド型のサービスモデルです。代表的なサービスは、GmailやGoogleドライブなどが挙げられます。アプリの保守やアップデートはサービス提供者側が対応するため、利用者は管理作業を行う必要がありません。また、障害対応やバージョン管理も任せられるので、運用の負担が少ない点も特徴です。
ただし、機能の追加やカスタマイズの自由度は限られており、セキュリティ対策もサービス側の仕様に依存します。料金は月額制のサブスクリプション方式が一般的で、初期費用を抑えつつ利用規模に応じたコスト調整がしやすく、個人や中小企業でも導入しやすい点が魅力です。
また、SaaS・PaaS・IaaSの違いを詳しく知りたい方は、関連記事「SaaS・PaaS・IaaSの違いは?定義やメリット・デメリットを解説」をご覧ください。
PaaS:アプリ開発に必要なプラットフォームを提供
PaaS(Platform as a Service)は、アプリケーション開発に必要なOSやミドルウェアなどをまとめてクラウド上で提供するサービスモデルです。代表的なサービスには、AWSやMicrosoft Azureなどが挙げられます。
PaaSのプラットフォームを利用すれば、自社で物理サーバーを用意したり、開発環境を構築したりする手間がなく、ブラウザ上からすぐに開発やテスト、デプロイの作業に取りかかることができます。
SaaSが「完成されたアプリケーションをそのまま使う」形式であるのに対し、PaaSはコードやフレームワークを自由に組み合わせられる点が特徴です。独自の機能を追加したり、外部サービスと連携したりできるため、柔軟なシステム構築が可能になります。
また、環境のセットアップや保守はクラウドプロバイダーが行うため、ユーザーは実装に集中でき、生産性の向上にもつながります。ただし、使用できる開発言語やデータベースがあらかじめ決まっている点に注意が必要です。
IaaS:インフラ機能をクラウド上で提供
IaaS(Infrastructure as a Service)は、仮想サーバーやストレージ、ネットワーク、OSなど、インフラの構成要素をまとめてクラウド上で提供するサービスモデルです。代表的なサービスには、Amazon EC2やGoogle Cloud Platformなどが挙げられます。
IaaSのサービスを活用することで、自社で物理サーバーを購入・設置する必要がなくなり、希望の構成を持つ環境を立ち上げられます。ネットワークやストレージの構成も細かく設定できるので、要件に応じた柔軟なシステム構成が実現しやすくなります。
また、仮想マシンの台数やスペックは導入後も調整しやすく、利用状況や事業の拡大に応じてスムーズに対応可能です。さらに、DNS管理やSMS配信、サーバーレス実行環境などの機能も提供されており、システム全体の設計と運用を効率化できます。
ただし、OSより上のレイヤーにあたるアプリケーションの設定や更新、アクセス権限の管理、セキュリティ対策などはユーザー側の責任となります。そのため、IaaSの導入には、技術知識と運用体制の準備が必要です。
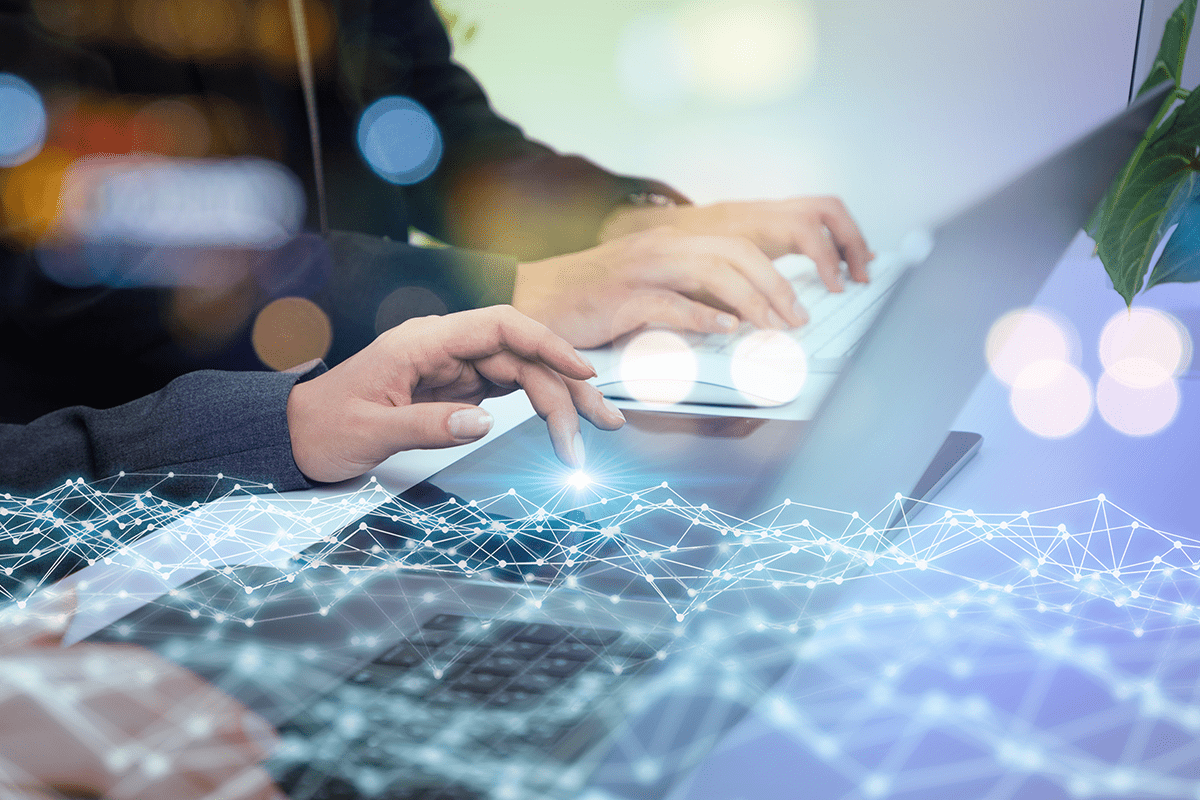
クラウドインフラのメリット
クラウドインフラには、主に以下のメリットがあります。
ここからは、代表的なクラウドインフラのメリットについて、それぞれ詳しく解説します。
アクセスに場所の制限がなくなる
クラウドインフラを導入することで、インターネット環境さえあれば、どこからでも業務システムにアクセスできます。自宅や出張先、サテライトオフィスなどからも、PCやスマートフォン、タブレットを使って作業が可能です。
オンプレミス(自社施設内にサーバーを保有すること)のようにVPNや専用ネットワークを構築する必要がなく、ブラウザ経由で安全に接続できるため、導入の手間も軽減されます。
さらに、クラウド上のデータは常に最新の状態に保たれており、複数の拠点にいるメンバー同士がリアルタイムで情報を共有できます。そのため、テレワークや外出中の対応も円滑に進めやすくなり、業務の継続性が高まります。
BCP(事業継続計画)の対策に有効
クラウドインフラは、地理的に分散された複数の拠点にサーバーを配置することで、災害や障害による影響を局所的にとどめる構成になっています。これにより、一部の拠点にトラブルが発生しても、全体のシステムが止まるリスクを大幅に軽減できます。
主要なクラウドプロバイダーでは、ストレージと仮想マシンの分離管理を行い、冗長化やバックアップ、災害復旧(DR)といった機能を標準で備えています。万が一システム障害が発生しても、別リージョンで仮想マシンを立ち上げ直すことで、迅速な復旧が可能です。
オンプレミスの場合、物理サーバーの損傷がそのまま業務停止につながることもありました。しかしクラウド環境であれば、こうしたリスクをあらかじめ分散できるため、BCPの一環として組み込みやすく、現実的な対応策になります。
特にパブリッククラウド(不特定多数のユーザーに提供しているクラウドサービス)は、柔軟にリソースを拡張できる分散型構成を採用しており、平常時の安定稼働と非常時の耐障害性を両立できる点で、事業継続を検討する際に有効です。
セキュリティ性能が高い
クラウドプロバイダーは、専門のセキュリティチームを常駐させており、暗号化・アクセス制御・脆弱性の診断など、複数の層にわたる対策を継続的に実施しています。ユーザー側でポリシー設定やアクセス権限を適切に管理することで、クラウドの機能と組み合わせた強固なセキュリティ環境を整えることが可能です。
データの冗長化や自動バックアップ機能も標準で備わっており、障害や災害時にもサービスを継続できる信頼性が確保されています。
また、オンプレミスと比べて、物理機器の保守やセキュリティアップデートが自動化されている点もメリットのひとつです。
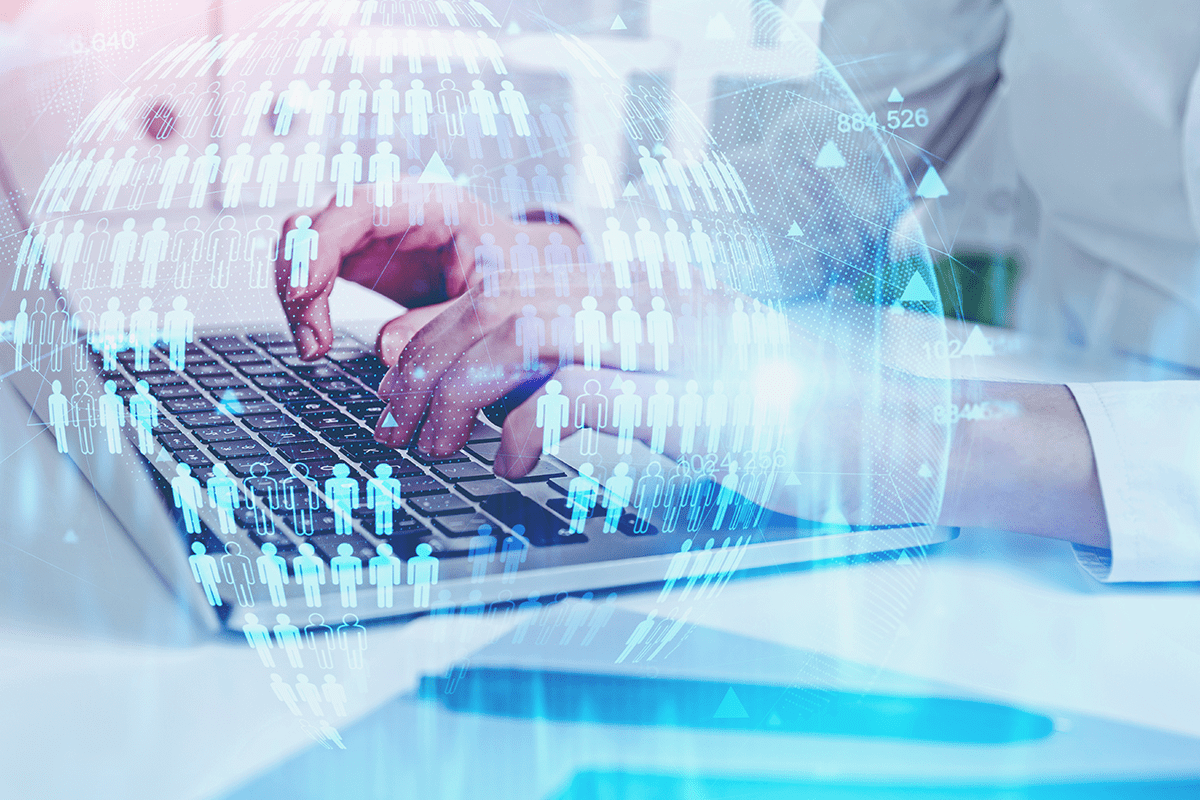
クラウドインフラのデメリット
クラウドインフラには主に以下のデメリットも存在します。
ここからは、クラウドインフラのデメリットについて、それぞれ詳しく解説します。
オンプレミス型に比べて拡張性が低い
クラウドインフラは、クラウドプロバイダーが提供する仕様に沿って利用する仕組みです。そのため、オンプレミスのようにハードウェア構成を自由に設計したり、細かくカスタマイズしたりすることは基本的にできません。
一方で、オンプレミス環境であれば、自社の方針や将来の見通しに合わせて構成を柔軟に決めることが可能です。業務内容によっては、高い制御性や独自の拡張性が求められるケースもあります。こうした場合には、クラウドの標準仕様がかえって制約となることがあります。
インターネット環境を整備する必要がある
クラウドインフラを利用するには、インターネット接続が欠かせません。また、インターネット回線の品質が十分でない場合、パフォーマンスが大きく低下する恐れがあります。
特に、大容量データの送受信やリアルタイム性の求められる業務では、通信速度が遅かったり接続が不安定だったりすると、業務そのものに支障が出ることもあります。
そのため、クラウドインフラを前提としたシステム設計では、通信インフラの整備や監視体制を含めた運用設計が重要です。加えて、モバイル端末やリモート環境から快適にアクセスするには、通信の速度と安定性をしっかり確保する必要があります。
クラウドインフラの成功事例
クラウドインフラの導入を検討する際は、実際に導入して成果を上げた企業の事例を参考にすることが大切です。導入目的や活用方法、得られた効果を把握することで、自社の導入計画にも具体的なイメージが持てるようになります。以下では、クラウドインフラの成功事例を紹介します。
AWSを活用したデータ基盤のクラウド移行と利活用促進
NTTドコモは、オンプレミスで運用していたデータ基盤を、わずか7か月という短期間でAWSへ全面移行しました。これにより、迅速かつ柔軟な分析環境の構築が可能となり、全社的なデータ活用の体制が整えられました。
移行後は、業務部門ごとのニーズに応じた環境を提供する「データ分析Lab」を立ち上げたことで、利用規模は従来の13倍にまで拡大しました。分散管理されていたExcelのデータも、統合データカタログに集約されたことで、データの所在や意味をすぐに把握できるようになり、業務の効率と利便性が向上しています。
また、クラウド特有のコスト課題には「FinHack」と呼ばれる社内プロジェクトを通じて対応。利用部門との連携によって、約30%のコスト削減とガバナンス強化を両立しました。環境構築にかかる期間も、従来の約半分となる3か月に短縮され、スケーラビリティや開発スピードも飛躍的に向上しています。
さらに、ツール選定やアカウント管理などを各部門が自律的に行えるようになり、組織全体のデータ活用力が底上げされました。現在は、NTTコミュニケーションズなどグループ企業への展開も進めながら、全社的なデータ活用戦略の推進に取り組んでいます。
Google Cloudを活用して製造現場向けAIプラットフォームを構築
トヨタ自動車では、製造現場のスタッフ自らがAIモデルを開発・活用できる「AIプラットフォーム」を構築し、現場主導のデジタル化を推進しています。実務に即したAI活用の民主化を目指し、誰でも使いやすい仕組みづくりに取り組んでいます。
プラットフォームの基盤には、Google Cloudとオンプレミスを組み合わせたハイブリッドクラウドを採用。これにより、柔軟な開発環境とGPUコストの最適化を両立しています。
また、AnthosやGKE(Google Kubernetes Engine)、Container Analysis、Binary AuthorizationといったGoogleの各種サービスを活用し、セキュリティを確保しながらも、運用負荷の少ないCI/CD環境を実現しました。
ユーザーインターフェース(UI)は、実際の利用者である現場スタッフの意見を取り入れながら、スクラム開発方式で改善を重ねています。実演とフィードバックを繰り返すことで、潜在的なニーズにも応えられる設計に仕上げています。
すでにこのAIプラットフォームは、目視検査や設備の異常検知といった業務の自動化に活用され、複数の拠点で導入が進んでいます。その結果、スタッフの業務がより高付加価値な領域にシフトし、全体の生産性向上にもつながりました。
今後は、時系列データの解析や自然言語処理といった分野への対応も検討されており、社内外での活用拡大に向けてプラットフォームの継続的な進化が予定されています。
まとめ
今回の記事では、クラウドインフラの意味や構成要素、代表的なサービスモデル、メリット・デメリット、成功事例などについて解説しました。クラウドインフラとは、サーバーやネットワークといった物理設備を仮想化し、インターネット経由でオンデマンドに提供する「ハードウェアとソフトウェアの基盤」です。
場所にとらわれないアクセス性やBCP対策、コスト削減、セキュリティ向上などのメリットがある一方で、カスタマイズの制約やネットワーク環境への依存といったデメリットも存在します。自社の目的に合ったサービスを選び、運用体制をしっかり整えることで、その効果を十分に引き出すことができるでしょう。


