サーバーの仮想化は、企業のITインフラを変革させる手法として注目を集めており、導入することで、運用面やコスト面など、さまざまなメリットを得られます。
その一方で、「システム投資の負担はどれくらい?」「仮想サーバーの実装手順は?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで今回は、サーバー仮想化の意味やメリット・デメリット、仮想化させるタイミング、仮想サーバーの種類、導入方法などについて解説します。
サーバー仮想化とは?【サーバーを分割する仕組みのこと】
サーバー仮想化とは、「物理サーバー1台から複数の仮想化したサーバー環境を作り出す技術」のことです。
仮想化を実現できるソフトウェア、「ハイパーバイザー」などの物理サーバーへ導入すれば、個別の仮想サーバーとして活用できます。
仮想サーバーには、異なるOSやアプリケーションを設定して運用が可能です。
ハイパーバイザー型以外にも、仮想サーバーには「コンテナ型」「ホストOS型」といった種類があります。
詳しくは後述の「仮想サーバーの種類とそれぞれの導入方法」をご覧ください。

物理サーバーとの違いは分割の可否やコストなど
物理的に存在するサーバーは「物理サーバー」と呼ばれ、企業データの管理や保存に利用されます。物理サーバーはリソースが不足した際や新規導入時には、ハードウェアの追加が必要になります。
一方、ソフトウェアの制御により複数の環境を統合・分割できるのが仮想化サーバーの特徴です。それぞれの違いをまとめると、以下の通りです。
仮想サーバー | 物理サーバー | |
目的 | 単一の物理サーバーで複数のサーバー機能を提供する | 単一の物理サーバーを直接利用する |
特徴 | ・リソースを効率的に活用できる ・柔軟に環境構築が可能 ・可用性が高い | ・リソースを占有できる ・ハードウェアを自由に選択 ・組み合わせることができる |
機能性 | ◯ | ◎ |
コスト | ◎ | ▲ |
サーバーを仮想化させるメリット
サーバーを仮想化させることで、主に以下のメリットを得ることができます。
ここからは、サーバーを仮想化させるメリットについて解説します。
サーバー運用を効率的に行える
先述の通り、サーバー仮想化をすることで、複数のサーバー環境を1台に集約し、リソースを最大限に活用できます。その結果、サーバー運用を効率的に行うことが可能です。
仮想環境のテンプレート作成や別マシンへのシステム移設といった効率化も実現し、管理作業の負担を減らせます。
運用コストを減らせる
サーバー仮想化のメリットのひとつは、運用コストを削減できる点です。物理サーバー1台からでも複数の仮想環境を構築できるため、ハードウェアや維持管理にかかるコストを抑えられるでしょう。
さらに、電力の使用量を削減できるため、毎月の光熱費も抑制できます。
古いシステムを引き続き利用できる
サーバー仮想化のメリットには、古いシステムを引き続き活用できる点も挙げられます。古いシステムでは、最新のOSへのアップグレードが難しい場面が増えてきます。
しかし、サーバー仮想化を導入することで、この問題を解消し、新しいアプリケーションも快適に利用できるようになります。
その結果、OSのバージョンに関係なく、常に最新のシステムを構築することが可能です。
ちなみに、既存システムの老朽化が発生した際、そのシステムを管理できる人材や技術がない企業が増えることが国際的に問題視されています。 詳しくは、「2025年の崖とは?問題視される理由から対策をわかりやすく解説」をご覧ください。
災害の対策にもなる
サーバー仮想化は、BCP(事業継続計画)の観点からも有用です。自然災害でシステムの運用が困難な場合でも、サーバー仮想化を導入しておくことで、業務を早期に再開できる可能性が高まります。
たとえ運用システムへのアクセスが制限されても、別の環境から復旧作業を開始することが可能です。仮想サーバーにバックアップデータがあれば、素早い業務再開へとつながっていきます。
必要に応じて拡張できる
必要に応じて拡張ができる点も、サーバー仮想化のメリットです。サーバーを拡張する際、物理サーバーでは新しいマシンを購入する以外に選択肢がありません。
物理サーバー環境を構築する場合、データセンターのスペース確保から本番稼働まで少なくとも1ヶ月程度はかかります。一方、サーバー仮想化では、リソースの余裕さえあれば瞬時に拡張に対応できます。
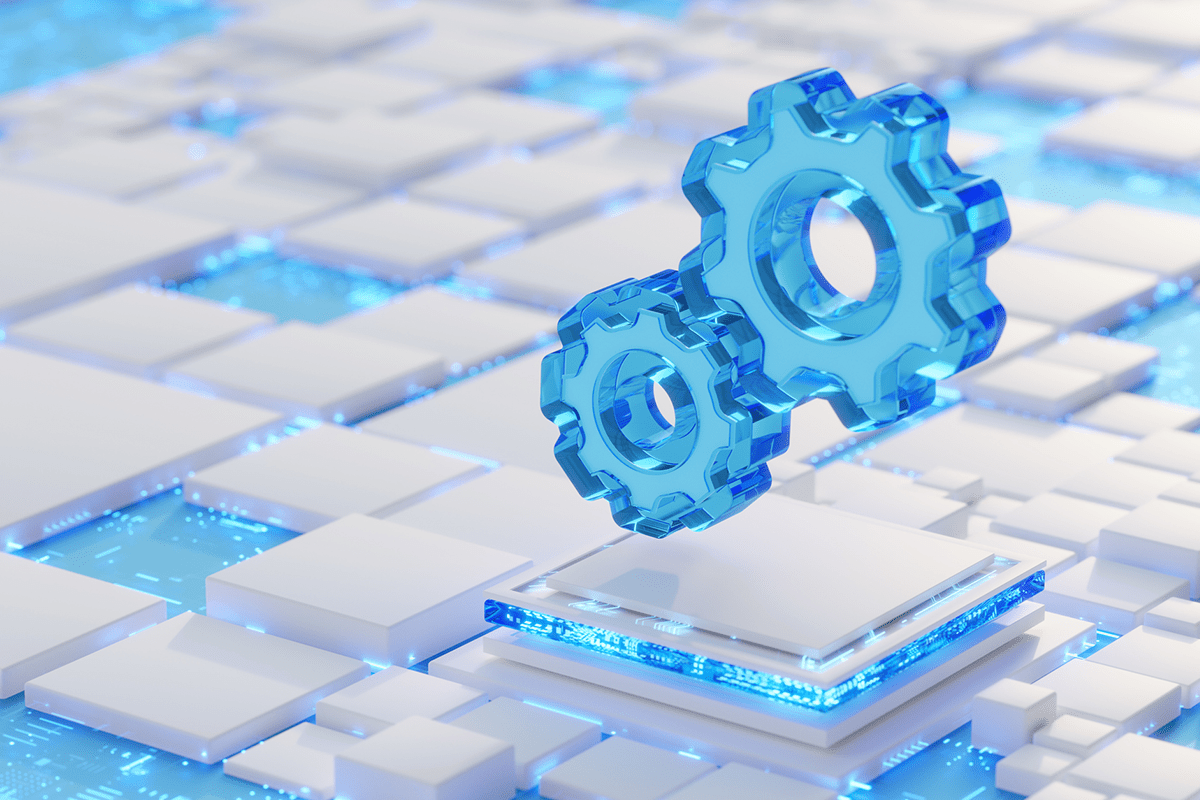
サーバーを仮想化させるデメリット
サーバー仮想化には多数のメリットがある反面、以下のようなデメリットも存在します。
適切なリソース配分が必要
サーバー仮想化では、物理サーバーのハードウェアのリソースが重要になります。リソースの余裕がない状態で仮想化を進めると、サーバーの性能低下を招きます。
そのため、各仮想サーバーへの処理能力の割り当ては、適切な配分が欠かせません。サーバーやストレージの性能、データ転送量を踏まえたネットワーク設備の状況を事前に把握しておけば安定した運用につながります。
専門知識が必要
サーバー仮想化のデメリットのひとつが、専門知識が必要なことです。仮想サーバーの運用には、システムの基本的な仕組みと管理方法への理解が求められます。
また、仮想サーバーのシステム障害に対応するためにも、高度な専門知識を持つエンジニアの確保が望ましいでしょう。サーバー仮想化を導入する際は、運用面を見据えた長期的な体制づくりを進めていくのがベストです。
より強度なセキュリティ対策が必要
仮想サーバー物理サーバーでは対策するセキュリティの内容や範囲が異なります。仮想サーバーのシステムを深く理解していないと、さまざまなトラブルに対応できません。
複数のOSが動作するサーバー仮想化の環境では、セキュリティ対策が物理サーバーと比較すると複雑です。そのため、より強度なセキュリティ対策が求められます。

物理サーバーに比べると性能は劣る
仮想サーバーは1台の物理サーバー内で複数稼働させるため、性能麺では物理サーバーと比べると理論上は劣ります。データ処理の負荷が増加すると、仮想環境では処理速度の低下につながる傾向があります。
サーバーのリソース配分によって性能が左右されるため、安定した運用には技術的な工夫が求められます。ただ、適切な設置を行い、リソース配分を行うことで、物理サーバーと同等の性能を発揮できます。
大規模環境でないと活躍しにくい
サーバー仮想化は、大規模環境でないと活躍しにくいという側面もあります。小規模なシステムでは、サーバー仮想化よりも物理サーバーの方がコスト面などで優位になる傾向にあります。
仮想サーバーの運用には専門的な人材が求められ、採用にかかるコストも必要になります。そのため、物理サーバーで運用していた場合よりも負担が増える可能性もあります。サーバーの仮想化を導入する際は、システムの規模を考慮しておくことが重要です。
サーバーを仮想化させるタイミング
サーバーを仮想化する際には、適切なタイミングを考慮することが重要です。ここからは、サーバーを仮想化させるタイミングについて解説します。
現行のシステムが古くなってきたとき
現行のシステムが古いと感じたときは、サーバーの仮想化のタイミングといえます。老朽化が進んだサーバーでは、さまざまな問題が発生する可能性が高まります。
サーバー仮想化を導入することで、処理能力が向上し、メンテナンス性も高まるため、業務改善につながるでしょう。また、新しいシステムへの切り替えにより、従来の運用上の課題も解決できます。
サーバーの電力消費が多いと感じてきたとき
サーバーの電力消費が多いと感じてきたときは、サーバー仮想化の導入を検討するのもいいでしょう。ハードウェアの集約により、複数のサーバーを一元管理し、消費電力の削減につなげられます。
開発環境や本番環境の効率化も進み、運用管理の負担も軽減されるでしょう。物理サーバーの統合で、全体的な消費電力量を抑制し、月々のコストダウンも実現できます。
システムごとにサーバーが必要なとき
システムごとにサーバーが必要になった際は、サーバー仮想化をするタイミングです。サーバー仮想化により、開発環境の構築や各種システムの準備時間を大幅に短縮できます。
複数のサーバーを柔軟に準備できるため、プロジェクトごとの環境整備がスムーズに進められます。各担当者に応じたカスタマイズ環境も即座に用意でき、開発効率の向上につながるでしょう。また、新規システムの立ち上げ時も、サーバー仮想化で素早く対応が可能になります。
仮想サーバーの種類とそれぞれの導入方法
仮想サーバーには、「ハイパーバイザー型」「コンテナ型」「ホストOS型」などの種類があり、それぞれ導入方法が異なります。ここからは、仮想サーバーの種類とそれぞれの導入方法について解説します。
ハイパーバイザー型
ハイパーバイザー型とは、物理サーバーのハードウェア層に仮想化ソフト「ハイパーバイザー」をインストールし、複数の仮想環境に分割する方式です。
この方式により、高速な処理パフォーマンスを実現できます。一方で、運用面では複数の仮想サーバーを1台の物理サーバーで管理するため、コストの見積算出に時間がかかります。
コンテナ型
コンテナ型方式では、アプリケーション本体や設定ファイルなどの環境を、コンテナという仮想環境内で構築する方式です。物理サーバーのOSにコンテナエンジンをインストールして、運用と管理を実施しています。
環境のコピーが容易なため、設定作業にかかる手間を軽減できる点がメリットです。ただし、ベースとなるOSに対応していない場合は利用できないため、これがデメリットとなります。
ホストOS型
ホストOS型とは、物理サーバー上のOSに仮想化ソフトをインストールして、仮想サーバーを作成する方式です。既存のハードウェアをそのまま活用でき、運用中のサーバーにも導入できます。
初期の管理体制を大きく変えずに済むため、コストの抑制につながります。1台のマシンで複数の仮想環境を動かすため、全体の処理速度が低下する傾向がある点がデメリットです。
まとめ
今回の記事では、サーバー仮想化の意味やメリット・デメリット、仮想化させるタイミング、仮想サーバーの種類などについて解説しました。サーバー仮想化は、物理サーバー1台から複数の仮想環境を生み出す技術です。
主にハイパーバイザー型、コンテナ型、ホストOS型の3種類があり、それぞれに特徴があります。メリットとして、サーバー運用の効率化、コスト削減、古いシステムの継続利用、災害対策、柔軟な拡張性が挙げられます。
特に業務効率の面では、環境構築の時間短縮やリソースの最適活用により、大幅な生産性向上が期待できます。


